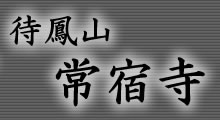�����̕W�� 2023�N
2023�N�@�u12���̕W��v
������
�\�\�\ ��h��
�挎�A���m�点�v���܂������A���������̂��ߓ��T�C�g�̍X�V�����x�݂����Ē��������A��낵�����肢�\���グ�܂��B
2023�N�@�u11���̕W��v
���S�̒��ɈߐH����@
�ߐH�̒��ɓ��S�Ȃ�
�\�\�\ �w�`�q��S�����x�`����t��
�u �������߂�S������ΈߐH�̂��Ƃ͎��R�Ƃ��Ă���B�����ߐH�̂��Ƃ���ǂ����߂Ă����瓹�����߂�S�͋N���Ȃ��B�v
�@������A�������Ő��́A���{�̕����E���ĕ҂��ׂ��A�����ʂ蓌�z�������閈���𑗂�悤�ɂȂ�܂��B
�@�܂��͒����Ŋw�������L�߂邽�߂ɓV��@���J���A�P�̏@�h�Ƃ��Đ����ɔF�߂Ă��炦��悤����ɓ��������܂��B�����āA���琧�x�𐮂��A��i�̈琬�ɓ������A��b�R�̎{�݂��[�������Ă����܂����B����ɂ͎���֓����B�ɂ܂ŏo�����A�y�n�̐l�X�ɐ�����`���ĕ������̂ł��B
�@�����犯������闧��Ƃ͂����A�����炨���������Ă�����Ȃ����������Ƃ͑z���ɓ����܂���B
�@�ł�����A�u�������߂�S������A�o�ϓI�Ȃ��Ƃ͎��R�Ƃǂ��ɂ��Ȃ�v�Ƃ����̂́A�Ő��̐S�̒ꂩ��o�����t�������̂ł��傤�B
����͓`����t�Ő��́w�`�q��S�����i�ł������������j�x�̒��̂����t�ł��B
�@���S�Ƃ́A�������w�ю��H����S�������A�ߐH�Ƃ́A�ߐH�Z�̐������̂��Ƃł��B
�@�������߂ēw�͂��d�˂����S������A���̖ړI��B������̂ɕK�v�ȈߐH�Z�́A���̂��Ƃ��Ă���B
��������琶���Ɍb�܂�Ă��Ă��A���̐����̒�����́A�ނ������ɗ�����āA�������߁A���������߂悤�Ƃ���S�͋N���Ă��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@���݂̎������̐����́A�����I�ɑ�ϖL���ɂȂ�܂����B�s�i�C�Ƃ����Ȃ���A�J�Ԃɂ͕������Ă��܂��B�������A�ǂ��ƂȂ��s�������Y���Ă��܂��B�����A�o�ρA����A��ÁA�����Ȃǂɑ���l�X�ȕs�M���Q�����Ă��܂��B
�@����ɁA�Ȋw�Z�p�̐i���͑����̗������������ɂ����炵�����ʁA�l�X����z���͂�D���A�l���v�����S�����ቺ�����Ă��܂��܂����B�s���ɋ���A���Ȓ��S�Ŋ��ӂ̐S���������l�Ԃ������A�v���ʂ�ɂȂ�Ȃ��Ƃ��̕s�����A���l�ւ̉��݂ɓ]�������܂��B���X�ƋN���鋥���Ȏ����̔w�i�ɂ́A�l�i��{�����炪�y������Ă������Ƃ����邩��ł͂Ȃ����傤���B
�@�����̒��Ɋm�ł���u�M�v�������Ȃ����Ƃ��A����s���̑傫�ȗv���̈�ɏグ���܂��B���Ɉ͂܂�ĕ֗��ɐ����邱�Ƃ��A�{���ɐl�Ԃ炵�������邱�ƂȂ̂��A�l���Ȃ��������ɂ��Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�V�؋����V�t���u����ł����˂Ε��@�ɂȂ�ʁB�i�}�E���ł����Ă��Ă͑ʖڂ���B�v
�@�u�Ȋw�̔��B�̂��ɁA�l�Ԃ������Ƃ��G���N�Ȃ��Ă��Ȃ��̂͂ǂ������킯���v
�u����Ȃɗ����Ԃ��āA����ȂɃo�J�ɂȂ��Ă��������̂��l�ԂƂ����o�J���m�ł���B�v
�ƁA�������Ⴂ�܂����B
�@40�ケ�납��T�̋ɂ݂Ɋׂ�A���T�O���̓��X�𑗂�A�V�ؘV�t�̌�{���ËL������A�ǂ�ł���܂�������45�ňӂ������āA�Əo�����s���܂����B���̎��͕����ʂ�u����ł����܂�Ȃ��v�Ǝv���l�߂ē��������{�ɂ���Ă����̂ł��B
���Z�E�����t���V�ؘV�t�̈���q�ł����B�܂��ɕ����ʂ�u���S�̒��ɈߐH����A�ߐH�̒��ɓ��S�Ȃ��v�Ƃ���������̌��Ȃ����������Ԃ�ł����B�u�������߂�S�v���l��{���������������Ƃ����L�������c���Ă��܂���B�ȑO�ɂ����̃y�[�W�ɏ������Ǝv���܂����A�䎩���̂����g���Ă���Q����|���鎞�A�V�[�c�ł���ނ悤�Ɏg���Ă���ꂽ�̂ł����A�u��������ƌ��̂��̂�����Ȃ�����v�Ƃ�������������ɖ{���Ƀr�b�N�����܂����B���i�����̎g���z�c�Ȃǂ́A���R�����̕z�c�Ƃ������Ɏv�����Ƃ̕������ʂ��Ǝv���̂ł����c
�i�Əo���Ă������A���R�A���i�g���Ă����z�c�������Ă��܂����̂�💦�j
�H���͊�{�I�Ɍ��čؐH�ł��B���Ă�30�L���̑܂����I�ɑ����Ă�������������܂����B����͑��̕���������̂ŁA���X�ɍs���ĉ��������Ƃ������Ƃ�S�����Ȃ����ł����B
�����A�����ɂ�������͌��čؐH�ł������A���̕��Q�̖ʂɂ����X�C�t���n�߂Ă�������ł����B�����t�͐g�����P�T�O�p���炢�ŁA�̏d��30�s������������܂���ł����B�̒��������ėǂ��Ƃ͌������A���炩�ɉh�{�����ł����B
����ŁA�����������Ă���ŏ��̏T�ɗ����܂����B���ɋߏ��ɂ���R�C�����ċ@�ɂ����āA���Ă𔒕Ăɐ��Ă���悤�ɂ��܂����B��������������A���ƈꏏ�ɐH�ׂ�悤�ɂȂ��Ă���݂�݂�̏d�������A��F���悭�Ȃ��Ă��܂����B�Ȃɂ����ȑO�͈�N�ɐ��x�A���M���ĐQ���ނ��Ƃ��������悤�ł����A�������Ă���́A��x�������������Ƃ͂Ȃ��Ȃ�܂����B
�S���Ȃ�����ŁA��i�����ɁA���ɑ��銴�ӂ̌��t���Ԃ��Ă����̂����܂����B
�{���͎��̕������A���ꏊ��^���ĉ����������ƂɁA���t�ł͐s�����Ȃ��قNJ��ӂ��Ă���܂��B
��͂�A����ԉ�����l�́A�ƌ����ΐ��Z�E�ł����A�悭�����̒��ɂ��閲�����܂��B����u��������v�̉Ƃɂ��Q��Ɏf���āA���̓��ނ͎d���x�݂������̂ʼnƂɂ����̂ł����A���̖T�ɉB���l������ƌ����A�ƂĂ��������Ȃ�܂����B
���������Ē����đ������̂Ŏl�����I���o���܂����B����40��Ő^�ʖڂ�����������������ӂ��҂ɂȂ�A������ō��킹��炪�Ȃ����炢���炵�Ȃ������Ԃ�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B�ł��̂ŁA���Z�E�͎��̂�邱�ƂȂ����Ƃ��S�z�ŖT�Ō������Ă���̂ł��傤�B
�����A������V�ؘV�t�A�����V�t�Ƃ̌n���̓`���ŁA���Ă��邱�Ƃ�����܂��B�u���z�{��x�O�����������v�ł��B�V�ؘV�t�������V�Ȃǂ𗊂܂ꂽ���A�������ꂵ�����̂����V�Ȃǂ́A�S�����z�{�����łȂ������Ǝf���Ă���܂��B
�����A�����V�A���@���Ȃǂ̌�˗����鎞�ɂ́A�K�����z�{�̊z����܂����A�u���u�Łc�v�Ƃ��������Ă���܂��B
����Ȃ̂ɁA���܂ŁA�����閾���̐H�ו��ɂ������������ɂȂ������Ƃ��Ȃ��̂́A�܂��ɓ`����t�l�̂��������ʂ�Ȃ̂��Ǝv���܂��B
�V�t�͂��̂悤�ɂ�����������Ă��܂��B�u�������߂ɐH�����A�H�����߂ɓ������A���ꂪ�厖�Ȃ��Ƃł���B
�����Ă��̎҂͐H�����߂ɓ����B����ł͐l�Ԉꐶ���ɂ�����B����͂���������ŁA����Ȑl�Ԃ͂܂��Ƃɍ������㒎�̓����c�c���ɑS���g����Ƃ��������Ȃ݂̐l�ԂƂ���˂Ȃ�ʁB�����͂Ȃ�炩�̎g���̂��߂ɖ����Ȃ��̂ŁA���̂��߂ɂ����ǂ����Ă��H�ׂȂ���Ȃ��̂ł���B�v
�V�t�l�ɂǂ����Ă�����������āA���T���ɍs�������A���傤�Ǎ��T���I������Ƃ���ŁA�V�t�l���o�Ă��炵���Ƃ���Ƀo�b�^���������������ł��B���܂�̐_�X�����ɂւ��ւ��ƍ��荞��ł��܂����A�ƌ����l�Ɋ��x�ƂȂ��f���܂����B
���āA�ˑR�ł����A���̓x�A�ɗ���S�ʉ��z���A����܂߉i�㋟�{�_�Ƃ��Ă����S�̂����Ȃ������ƂɂȂ�܂����B����ɔ����A�����̃E�F�u�T�C�g����V����v��ł��B���N���ɂ͉��Ƃ��������Ǝv���Ă���܂��̂ŁA���炭�X�V�̕��͂��x�݂����Ē��������A��낵�����肢�\���グ�܂��B�����ԁA��R�̕��ɁA��ǂݒ����S���犴�Ӑ\���グ�܂��B�L���������܂����B�A�h���X�͕ς��܂���̂ŁA���܂ɐV������h���̉f�����A�b�v����Ă��邩�A�`���Ă݂ĉ������܂�<(_ _)>�@ ��������悤
2023�N�@�u10���̕W��v
��c���{�����Ȃ���
�a�C�ɂȂ�̂�
�\�\�\ �V���o�[�o�[�`�̗�P
�����A���߂Ɏf���Ă����Ƃ̂��b�ł��B��N�A���̌�Ƃ̉��l���O�Ȏ�p�����A���������@�Ȃ����܂����B���̌�͂����������A�܂����̂悤�ɁA���Q��Ɏf���Ă���܂����A������Q��Ɏf�������A�w���@�������ɁA�e�ʂ̕�����u��c���{�����Ȃ�����a�C�ɂȂ�v�ƌ���ꂽ�x�Ƃ��������A�����ꂽ�����łȂ��A�{�肪���ݏグ�Ă��܂����B���������A�̂����l�Ԃɂ��̂悤�ȉ��̍������Ȃ��A�����߂Ȃ��ƂC�Ō�����l�Ԃɑ��ċ��낵�������܂����B
�����A����������Ƃ��Q�肵�A�njo���Ă���܂����A�����̂���l������Y��D���Ƃ������Ƃ�����A��Ƃ������d������������ƂȂ����āA�����Ȃǂ��A���ꂢ�ɊD���炵���Ă���܂��B�ǂ��炩�����A�ނ��낱���܂łł��Ă����Ƃ̕������Ȃ��Ɗ�����قǂł��B
���ԓI�ɂ́A�u��c���{�����Ȃ��ƕa�C�ɂȂ�v�Ƃ������Ă��邱�Ƃ��m��Ȃ��킯�ł͂���܂��A����͖{���̂��ƂȂ̂ł��傤���H
��ʓI�ɐ�c���{�Ƃ����ƁA
�P. ����̕��d�Ɉʔv���J��A���т₨�Ԃ������A������������B
�Q. ����n�ɍs���Ă���Q�������B
�R. �N���@�v�⌎�����ɑm�����Ă�ŋ��{����B
�Ƃ��������Ƃ��������܂��B
�ł��̂ŁA���̂悤�Ȃ��Ƃ��ł��Ȃ��ƁA��c���{������Ȃ��A�ƌ����邱�ƂɂȂ�̂�������܂���B
�����āA���ꂪ�G�X�J���[�g����ƁA�K���Ȃǂ̕a�C�ɂȂ�����A���̂ʼn����������A�Ƃɂ����s�^�Ȃ̂́A��c���{�����Ȃ����炾�Ƃ��A�����o���l���K���o�Ă����ŁA�͂����茾���āu�A�u�i�C�v�ł��B
���������A���̂悤�Ȃ��Ƃ͐V���@���ł����邱�Ƃł��B
�u�����̐V�@���^���̑������A���݂̕s�K��a�C�̌������c�̗���M��̍�p�ł���Ɛ������A�����M��̏����̂��ߐ�c���{�����߂Ă���̂��A�Â�������M��M�Ɋ�b�����������̂Ƃ������Ƃ��ł���ł��낤�B�v
�i���p�F���}�Ёw���E��S�Ȏ��T�x��Q�Łj
�����̓��ꋳ��Ȃǂ́u��E�ɂ����c�̋ꂵ�݂����ł�����Ƃ��āA�u��c�������v�Ȃ���̂����邻���ł����c�@��̂���ɂ��̂悤�Ȏ��i������̂ł��傤���i�j
�V�����@���ɋA�˂����߂邽�߂ɂ́A�������͈����ł����A���̎肱�̎���g��Ȃ���Ȃ�܂���A���̂����́A������Ȃ�������܂���B
�������Ȃ���A���̃E�F�u�T�C�g�������Ƒ����Č�ǂݒ����Ă�����Ȃ�A������������Ǝv���܂����A�։��]���Ƃ������Ƃ́A�m���ɂ��鎖���ł��̂ŁA��c���{������ΏۂƂ����̂́A����ڂ��O�̎����ɓ�����\��������̂ł��B
�u��c���{�͕����̋����v�Ǝv���Ă���l������܂����A�����ł͂���܂���B
�N���Ƃ��ẮA���Ƃ��Ƒc�搒�q�̋������痈�����̂ŁA���A�W�A��тɍL�܂��Ă���K���ł��B
�l�͎��˂Ε�̉���ʔv�E���d�Ȃǂɗ��܂邱�Ƃ͂ł����A���ʂ܂łɎ���̂�����s���ɂ���āA���ʂ̓����ɂ��������āA�]�����Ă����܂��B
�@�l�Ԃ��n�㐢�E�ɐ��܂�Ă����̂͗�I�����̂��߂ł��B��I���݂̐l�ԂɂƂ��ė�I�������S�ĂƂ����Ă��ߌ��ł͂���܂���B
�@��I�^���̓����́A�ꌩ�ƂĂ����������̂Ɏv����̂��A���ʂ̖@���Ǝ��ȐӔC�̖@���ł��B
�����̐��������ۗ��ɉ����Ă��邩���Ȃ����A���̌��ʂ͑S�Ď����������Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ������Ƃł��B
�@�l�Ԃ��ۗ��ɉ��������݂�����A���ꂪ�ǂ������ƂȂ�A�ǂ�����(��I����)�������炳��A���Ɉ�������(���ȓI�s��)�����A��������(��I�����̃X�g�b�v�Ɨ�I�ꂵ��)�������炳���悤�ɂȂ�܂��B���ꂪ����(�J���})�̖@���ł��B
�@���ʂ̖@���Ɋ�Â��������ʂ͑S�Ė{�l�̐ӔC�ł���A���̃c�P�͂��ׂĖ{�l������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B���ꂪ���ȐӔC(���Ǝ���)�̖@���ł��B
�ł��̂ŁA�������̂�A�S�ɑ��Ĉ������Ƃ����Ă���A���d��_�I�Ɍ������āA�Ⴆ�A�a�C�������ĉ������Ɨ���A�������������āA�u�ǂ������z��������܂��悤�Ɂv�ȂǂƗ���ł������Ɍ��܂��Ă���̂ł��B
��I�^���ɋt�����������������l�́A�݂����猵�������n��������˂Ȃ�܂���B�ۗ��ɑf���ɏ]���Đ�����l�́A���I�Ȗʂɂ����Ă���I�Ȗʂɂ����Ă��A�K���ƖL��������ɂ��邱�ƂɂȂ�܂��B
�@�ۗ��ɋt�����������������l�́A��l�̐l�Ԃł��낤�Ƒ吨�̏W�c�ł��낤�ƁA�����ł��낤�ƍ��Ƃł��낤�ƁA�����͂��̑㏞��Ȃ���Ȃ�܂���B�ۗ��̓����͊����ł��B���̓����͐l�Ԃ̖ڂɂ͖ڂ��܂��A�����ƌ��ʂ͏�ɘA�����Ă��܂��B
�@���ʂ̌��ʂ͒n��ł����Ɍ����Ƃ͌���܂���B����̗�E�ɂ����Č����ꂵ�݂ƂȂ��ĕԂ��Ă�����A���̐��ŋꂵ�݁A�a�C�A�s�K�Ƃ����`�Ō���邱�Ƃ�����悤�ł��B
�@�܂��A����S�Ė����Ȃ�A����ŏI���Ǝv���Ă���l�B�́A�D������̐����������A����ł����Q�Ă��āA��ςȌ�������邱�Ƃł��傤�B
�@�������f�����Ă���܂��ʂ̌�Ƃ̉��l�̂����Ƃ��A���������ŐՎ�肪�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����̂ŁA���Ɛ�̂����d�Ɉꏏ�ɂ��܂肵�Ă���Ƃ����ꍇ������܂��B
���̂悤�ȃP�[�X�ł��u���d�ɕv�w���Ƃ̈ʔv��u���ƁA��c���m���P���J������̂ŕs�K���₦�Ȃ��Ȃ�B�v�Ƃ������M�����邱�Ƃ��m���Ă��܂����A����1�T�N�ȏエ�Q�肵�Ă��܂����A����ł͂��̂悤�Ȃ��Ƃ͋N���Ă���܂���B
�u�_�I����A���d�����ɒu���Ȃ��ƃo�`��������B�v����ȂǁA�}���V�����Z�܂��̕��͂ǂ����悤���Ȃ��A��̊K�̕��́A���̊K�̉Ƃ̐_�I���i��ԂƂ��āj���݂��ɂ��Ă��邱�Ƃ�����̂ł��B
����ł́A�}���V�����ɏZ�߂���Ȃǂ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��B
���̂悤�Ɍ`���I�Ȃ��Ƃ������ɂ���̂ł͂Ȃ��A��I�^���ɑ��ĊԈ���Ă��Ȃ������������邱�Ƃ��ł��d�v�Ȃ��Ƃł���Ǝv���܂��B
���M�ɘf�킳��Ȃ��悤�ɂ��邽�߂ɂ́A��������������I�m���������Ƃ���ł��B
��������I�m���͖��M����|���A�j�Z���m����M����l�X�����܂��B
���ꂩ��A����c�l�Ƃ����ƁA�������̂悤�Ɏv����������܂��A���R�Ȃ���A�����e�̂悤�Ȉ�ԋ߂����̑z����厖�ɂ��邱�Ƃ���ł��B
�����A���̃y�[�W�ɂ��o�ꂢ������N�q����̌�Ƃ̂��Ƃł��B�����e���S���Ȃ��āA�����Ƃ���������ƂɂȂ�A�����d�̐������̌�˗����܂����B���������I��������A�����d�̑O�ɂ������؋����u�ǂ����܂����H�v�Ƃ��������܂�����AN�q�������������u�v��Ȃ��v�Ƒ����Ȃ���̂ł��B����܂ł́A�䎩�����S���Ȃ��Ă��܂����̂Ŗ������̂�邱�Ƃ��A�䖝���ĖT�Ō�����Ă�������l�� �u���b�v�Ƃ��ē{���Ă��邱�Ƃ��͂�����`����Ă��܂����B���ʓI�ɂ͂��̖؋���N�q����̌�Ƃɂ���܂��̂ŁA�ǂ������Ǝv���Ă��܂��B
���������A�߂��̂���c�l��厖�ɂ��܂��傤�ˁB
2023�N�@�u9���̕W��v
40���߂����l�Ԃ�
�����̊��
�ӔC�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ�
�\�\�\ ��16��A�����J���O���哝�̃G�C�u���n���E�����J�[��
���ɂ́A�N����̎o������܂������A11�N�O�Ɋ��������A�S���Ȃ�܂����B���e�̍D�݂ŁA��l�Ƃ���������炸�A�w�K�@���q�����Ȃ��������A�Ȍ��w�𑲋Ƃ���܂ŁA�P�O�N�Ԃ̊w��������������܂����B
�o�͐��O�A���Ƃ͑S���Ⴂ�A�o�ϗ͂ɗD��A�w�K�@�̐l���������d����W�J���Ă��܂����B��h���̎Ԃ̓��B�b�c�ł����A�o�̓x���c�����Ă���܂����B���̂��Ƃ���������A�o�ϗ͂̃��x���̍�����@��������Ǝv���܂��B���c���Ƃ��ւ�������Ȃ���A���E�����щ���Ă���܂������A���̎o���A��قǂЂǂ��ڂɑ������悤�Ȍ��Ԃ�ŁAA�{�Ƃ�K�܂̂��Ƃ��u�����ȃ��m��v�Ɣᔻ�I�ɕ]���Ă���܂����B
�����g��A�{�ƂƂ͂��t�������͂���܂���ł������AA�{�a���͓�������u�A�z�̃A�[���v�ƌĂ�Ă����̂́A���m�̂��ƂŁA�C�P�Y�ƃA�z�̑g�ݍ��킹�ł�����AA�{�Ƃ̖��������邢���m�ɂ͂Ȃ�Ȃ��\���͂���܂����B
�@�o�����̂悤�ɐ\���Ă���܂����̂́A�o���S���Ȃ邸���ƈȑO�i�܂�20�N�ȏ�O�j�̂��Ƃł�����A�ŋ߂̂悤�Ȓ����̌�����A���j�̗L���Z�i�w�A���@���݂Ȃǂ̏���肪�A�܂��܂����ԓI�ɂ͋N���Ă��Ȃ����������ł��B
�@�������q�����Ȃɓ��w�������́A�܂��ʂ̋{�Ƃ̓��e���a���Ɠ����N���X�ɂȂ�܂����B�����g�́A�����A�S�����̂悤�Ȃ��Ƃ�m��܂���ł����̂ŁA���߂ĒS�C�̐搶���o�Ȃ���邽�߂ɐ��k�̖��O���A���ʂɌ\�����ɓǂݏグ�čs�������A���鐶�k�̂Ƃ���Łu�{�l�v�Ƃ����Ă�A�u�����v�Ƌ��������Ƃ��v���o���܂��B
���͏��a�R�X�N�ɏ��q�����Ȃɓ��w���܂������A�����͐�O���狳�����߂Ă��炵���搶����������Ⴂ�܂����̂ŁA��O�̍Z���Ȃǂ��F�X���������܂����B���ؑ��c���̕��X�����������̂ŁA�Z���ł͐��k����搶�ɂ����A���܂����A�ЂƂ��эZ����o��A�搶���琶�k�ɂ����A���邱�Ƃ͕��ʂ������A�Ƃ������Ƃł����B
�܂��A���ł��͂�����v���o�����Ƃ��ł��邨�b������܂��B������O��A�O�H�Ƃ����������̂���l�̂��b�ł��B�����͊w�Z�̎��Ɨ��͐U���Ȃǂł͂Ȃ��A���߂�ꂽ���ӑ܂ɓ���Ď����Ă��邱�ƂɂȂ��Ă��܂����B
���̌��ӑܒ�o�̎��A��l�������������̑܂ɓ���Ď����Ă������k�����������ł��B����l����u���O�̕s���ӂłȂ������̂�����A�����ō��Ȃ����v�ƁA�܈ꖇ�����Ƃ�������Ȃ����������Ȃ̂ł��B���ꂪ����������̂���l�̂��b���ł����B�搶�́A����������ƌ����Ă��A�����A���������炱���A�����̎g�����ɂ́A�����������Ƃ������Ƃ���������肽�������̂��Ǝv���܂����B
�J�ɂ́A�u�m�u���X�I�u���[�W�F�v�Ƃ������t������܂����A�����Љ�I�n�ʂɂ͂���ɂӂ��킵���`���������A�Ƃ����Ӗ��ł��B
���a�V�c���u��{�ɍc�����ڂ��ȁv�u�_�{�̎��͍_�{�̎q�v�Ƃ��������t�́A�m���ɋ��Ă����Ƃ������Ƃ����������Ƃ�����܂��B
���a�V�c�ƍ��~�c�@�͑�ώ��f�ɐ����Ȃ���A�u�䎩���B�������ł���̂������̂������v�Ə�������炨�������A�u�����䂩�����v�����������ł����B����ŁA�l�C�A�C�h�����̂悤�ɏT�����Ɏ��グ���A�ߑ���ɔN���疜�~�������܂��~�e�R�i��c�@�j�̐U���Ɂu�c�����䂪�߂Ă���v�Ƒ�ς��s���������悤�ł��B
��c�@�͖z���Ȑ����ԓx�ŁA����������l������̂ł͂Ȃ����Ɠx�X������Ă������Ƃ��������悤�ŁB���a�V�c��A�{�ɕs�M�������x��������Ă����̂́A�S�̉���̂ǂ����ŁuA�{�̕��e�͖��m�ł͂Ȃ���������Ȃ��v�Ƃ����^�O�����������Ƃ͗e�Ղɑz�������܂��B�Ȃɂ�A�{�̕��e��i�͂܂������Z�E���m�a���i�����j�Ǝ��Ă������Ȃ��̂ł�����c
�����^�O��A�{�܂ɑ��Ă��������ɈႢ�Ȃ��悤�Ɏv���܂��B���a�V�c�͌����ɂ��܂���C�ł͂Ȃ��A�ނ��딽�������悤�ŁA���̌��ʁAA�{�̍��\�́A���a�V�c�����䂳�ꂽ��ɂȂ�܂����B
�����āA���a�V�c�̊뜜�Ȃ����Ă������Ƃ��A�ŋ߁A�{���{���ƘI�ɂȂ��Ă��Ă���܂��B
�����N�������тɃl�b�g�̋L���Ŏ��グ���Ă��܂����A����ɑ���F�l�̃R���ɂ͍����̖{�����]���Ƃ���Ȃ�����Ă��܂��B
�R���P�F����Ӗ��ŔށiH�m�j���A���iK�q�j�̌�������̏o�_�����Ƃ��A���q�̓���Ґi�v��Ƃ��A�g�̏�ɍ����ǂ��납����ق��Ȃ����ƁA���ɂ��̉ł̍ی��̂Ȃ����h�S�̔�Q�҂Ȃ̂�������Ȃ��Ǝv���B�ł̋��h�S��}����@�I�K�����K�v���ƍl���܂��B��l�̐N�̌��₩�Ȃ鐬���̂��߂ɂ����ƕ��ނ��牓�����������ǂ��悤�Ɏv���B�ނ��{���ɖ]�ޓ�����܂���ׂ����ƍl���܂��B
�R���Q�F�����Ղ̊J��ł͕�e��^�����悤�Ȍ��p�ɗ͂̍��߂��悤�ȏ݂��ׂĂ܂�����
���̕��ɕK�v�Ȃ̂͂��o�܂��ł͂Ȃ��A�g�߂Ȃ��w�F�Ƃ̌𗬤�������ɗ�ނȂǁA���ʂ̍��Z�����i�����Ă����邱�Ƃ��Ǝv���܂��B
�R���R�F�e�����������Ȃ����[��������ɕ~���āA���̏�����ł��邱�Ƃ���������ᔻ����Ă��邱�Ƃ͂����������Ă���̂��Ǝv���B�����Ȏ����ɐi�w�܂Ō��Ɏ�肴������A�X�g���X�ɂȂ�Ȃ��킯���Ȃ��Ǝv���B���̂悤�ȋL�����o��̂�����Ӗ��e�̕s���̒v���Ƃ���ŁA����ׂ��Ƃ��������B�e�͎q���������̌��h�����̓���ɂ���悤�Ȃ��Ƃ������Ă͂Ȃ�Ȃ��Ǝv���B
���e�Ǝo�������D������ɌȂ̗~����Nj����邩��A���̂悤�Ȕᔻ�ɎN����Ă��܂��̂��낤�B��Ƃ������Ɋ��Y��Ȃ��������ʂł���B
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
K�܂��œ��肷�钼�O�ɏZ��ł����ڔ��̂RDK�̊w�K�@�̐E���Z����m���Ă��܂����A�������̏o�g�̐l�Ԃ����\�����̍��@�����Ă��邱�Ƃ͑z����₷�鎖�Ԃł����B�܂��Ɂu�g�̒��m�炸�v�̈ꌾ�ł��B
�܂��A�z�����̕��ƌĂ���16��A�����J���O���哝�̃G�C�u���n���E�����J�[���́A�u40���߂����l�Ԃ́A�����̊�ɐӔC�������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��v�ƌ����āA���ہA�t���̐l�I���u��v�ōs�����Ƃ����L���Șb������܂��B
A�{�͍݊w���ォ�琬�ѕs�U�ł��̂��납��u�A�z�̃A�[���v�ƌ����Ă��܂����B����͐��т݂̂Ȃ炸�A�m�\���x�f���āA�������Ԕ����ȕ\�������������鏊�Ȃ��Ǝv���܂��B�܂��ł͂��̐l����i����u�ʎ�v�ƌĂ�Ă���A����ȏ�Ȃ����炢�s�b�^���̕\���ł��B���̑��q���^�̎q�͊^�ŁA���Ƃ��e�C�̂Ȃ���ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B
����������ʂ��B���悤���Ȃ��\��Ă��܂��Ă���A���ꂪ����̍c����S����ƂȂǂƂ͓��ꂠ�肦�܂���B
�j�q�ɂ����c�ʌp����F�߂Ȃ��悤�ȁA�������̍c���T�͂����܂ł��ێ����Ă���Ȃ�A�V�c�Ƃ̑������낤���Ǝv���Ă��܂��BA�{�Ƃɍc�����ڂ邭�炢�Ȃ�A�������ނȂ����A�Ǝv�������ł��B
�ƁA�l�b�g�ŁA���̂悤�Ȏ�|�̃R�����g����x�������Ƃ�����̂ł����A�\�b�R�[�ō폜����Ă��܂��܂����B
A�{�ᔻ�����߂悤�Ƃ����{�����ɂ�錟�{�������Ă���悤�ŁA��̑�풆�̂悤�Ȍ��{�������Ă���ȂǁA���낵������ɂȂ������̂ł��B((((�G߄D�))))
2023�N�@�u8���̕W��v
�l�g�
���߁i���Łj�Ɏ�
���@�����
���߁i���Łj�ɕ���
�\�\�\ �O�A�˕�
��ʓI�ɁA�����ɋA�˂�����ۂɂ́A���E�@�E�m�����菊�ɂ��邱�Ƃ�錾����Ƃ����w�O�A�˕��x�����������邱�Ƃ���n�܂�܂��B
�����A�u���߉ނ��܂��h���A���̐����ꂽ�������Ɏ��A�����Ă��̋������w�Ԑl�X�̏W�܂���ɂ������܂��v�Ƃ�����|�̂����t������������̂ł��B
�u�l�g�i����j��i�����j���C���߁i���Łj�Ɏv
�@����́C���߉ޗl�̗L���Ȍ��t�ł��B�l�g�Ƃ͎������l�Ԃ̂��Ƃł��B�u�Ȃ��Ȃ����܂�邱�Ƃ�����l�ԂƂ��Đ��܂�邱�Ƃ��ł��Ă悩�����I�v�Ƃ����Ӗ��ł��B
�u���@������@���߁i���Łj�ɕ����v
�@����́A�u���̋��������͔��ɓ�����A�����͂������ĕ��������o����̂́A��ς��肪�������ƁI�v�Ƃ����Ӗ��ł��B
�ǂꂭ�炢��������ƌ����ƁA���o�̒��Ɂu�S�疜���i�����j�ɂ������i�������j�����Ɠ�i�����j���v �Ƃ���܂��B�u���v�Ƃ͒P�ʂł���܂��āA�l�\���l���̋���V�����O�N�Ɉ�x�����~��H�߂ł��̐ŁA�悤�₭���̋��������Ȃ�Ԃ��ꍅ�ƌ����܂��B
���̕S�疜�{�Ƃ����r�����Ȃ������o�āA���A���͕��̋����ɏo������Ƃ������ƂȂ̂ł��B
�ł�����A�u���̐g�����Ɍ����ēx������A����ɂ�����̐��Ɍ����Ă��A���̐g��x����v�Ƃ������ƂɂȂ�킯�ł����A
�u���̂ǂ����悤���Ȃ������Ŗ��������A�����鐶���։���J��Ԃ��Ă��������́A����Ɛl�Ԃɐ��܂ꂽ���̃`�����X���������āA���܂����ł����~���邱�Ƃ��Ȃ�������A������x�Ƌ~���邱�ƂȂ��A�ēx�։�̐��E�ɗ������݁A�i���̋�Y���J��Ԃ����ƂɂȂ�ł��傤�B�v
�Ƃ������ɂ��߉ޗl�͐����Ă�����̂ł��B
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
5��18���A�̕���o�D�E�s�쉎�V���e�^��(47)���A����̔��n���ňӎ��������낤�Ƃ�����Ԃœ|��Ă���̂���������A2�K�̃��r���O�ŁA�����œ|��Ă����̕���o�D�ŕ��̎s��i�l�Y����i76�j�ƕ�̊����l�i���̂��j���q����i75�j�͂���������S���m�F���ꂽ�B�x�����ɂ��ƁA��蒲�ׂɁu���e�����E����菕�����������ƂɊԈႢ�Ȃ��B�������e�̌��ǂ��Ď��E�������ł����v�Ƌ��q���Ă���Ƃ����B
�@���V���e�^�҂ً͋}�������ꂽ5��18�������A�x�@�̒���ɑ��A�����O���̓���17���ɉƑ��Řb�������u����Ő��܂�ς�낤�ƉƑ��Řb���A���e������������v�Ƃ�����|�̘b������B���̉Ƒ���c���s��ꂽ���́A���g�̃p���n����Z�N�n���^�f�Ȃǂ���w�����Z�u���x�̋L�����e�����V�����ɒm�炳�ꂽ�^�C�~���O�������B�{�i�I�Ȓ��悪�n�܂�������24���ɂ��A�x�@�Ɂu�S����}�����v�ȂǂƘb���A��e�̎��E���菕�������Ƃ��āA�x�����Ɏ��E�ق����e�^�őߕ߂��ꂽ�B
�ʋL���ɂ��A���V���͓��Y�w�����Z�u���x�����O���Ɂu����Ȃ��Ƃ������ꂽ��A���������Ă��Ă��Ӗ����Ȃ��B�Ƒ��݂�ȂŎ��̂��v�ƌ��ӁB�������u�������e�q�͕����̓V��@�̌h�i�ȐM�k�ŁA���ɑ��鋰�|�͂���܂���B�������������Ƃ��Ƃ͍l���Ă��܂���B�������͗։��]����M���Ă��܂��B���܂�ς��͂���A�Ɩ{�C�ōl���Ă��܂��v�Ƃ̎�������ʎ����ς���A�S����I�̂ł͂Ȃ����A�ƕĂ��܂����B
���͂��̋L����ǂ�ŁA����Ȉ�a�����o���܂����B���܂�ς���A����̐��E�ɂ��ẮA���̕W��ł���Ɏ��グ�ĎQ��܂�������A�������̃y�[�W��ǂ�Œ����Ă���F�l�ɂ́A�������Ē�����Ǝv���܂����A
���V���e�^�҂̋��q�́A���������E���m�肵�Ă���悤�ȊԈ������ۂ�^�����˂��A����͑�ԈႢ�Ƃ��āA����Ƃ������ɂ��āA�i���˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���܂����B
������s���ȓ_�́A�����_�ŁA�����̈�@�h����V��@�����牽�̃R�����g���悹���Ă��Ȃ����Ƃł��B
�O�q���܂����悤�ɁA���������l�Ԃɐ��܂ꂽ�̂ɁA���g�̃p���n���E�Z�N�n�����o��������ƌ����āA���e�܂Ŋ�������Ŏ�����I�ԂȂǁA���肦�Ȃ����Ԃł��B
���̃y�[�W�ʼn��x���o�ꂵ�Ē����Ă��܂��ō�����́u�V���o�[�o�[�`��v���A���E�ɂ��Ĉȉ��̂悤�Ɍ���Ă��܂��B
�u�����̐��E�����̐��E�ֈڂ�������Ƃ����āA���ꂾ���ō��ɉۂ���ꂽ�ӔC���瓦�������̂ł͂���܂���B���ꂾ���͖��m�ɒf���ł��܂��B
�命���͎��Ɍ��킹��Ή��a�҂̓����s�ׂł���ƌ����Ă悢�Ǝv���܂��B�ʂ����ׂ��`���ɐ^���ʂ�����g�ނ��Ƃ��ł����A���������l���Ă��邱�ƁA�܂莀��ł��̐���������邱�Ƃ����̋ꂵ�݂��瓦��邢���N�ȕ��@���ƍl����킯�ł��B
�Ƃ��낪�A������Ȃ̂ɑ��ς�炸����������B�����ē��ꂽ�͂��̐ӔC�Ƌ`���̊ϔO�����ς�炸�����ɂ��܂Ƃ��B���̐��_�I�������Í��̃I�[���݁A���ꂪ�O�E�Ƃ̐ڐG���Ւf���܂��B���̏�Ԃ��甲���o���Ȃ��܂܉��\�N�����S�N���ꂵ�ގ҂����܂��B
�@������ɂ���A���Ȃ��̍��͂��Ȃ����g�̍s�ׂɂ���ď������܂��B�݂�Ȏ����̎�Ŏ����̐l���������Ԃ��Ă���̂ł��B���������L�������͓̂�x�Ə����ς���킯�ɂ͂����܂���B���܂����͂����Ȃ��̂ł��B�����Ŏ�������������̂ł��B���̖@���͐�ł���A�s�ςł��B
�@�����炱�����́A�����܂Ŏ����ɒ����ł���Ȃ����ƌ����̂ł��B�����Ȃ鎖�Ԃ��{�l���v���Ă���قLjÂ����̂ł͂���܂���B���̋C�ɂȂ�ΕK�����������Ă��܂��B���̉��ɐ��ޗE�C���N���o�Ă��܂��B
�ӔC��S�����悤�Ƃ������Ƃ��]������āA���̕�������E����̉����̃`�����X�������܂��B�w������Ȃ��قǂׂ̉͂������ĕ��킳��܂���B�Ȃ��Ȃ�A���ׂ݂̉͂�����̈��Ƃ������炦�����̂�����ł��B�������Đ_�������̐l�Ԃɂ͂��ꂾ���̂��̂킹�Ă�낤���ƍl���āA���Ă����悤�ȁA����Ȃ��������Ȃ��̂ł͂���܂���B
�@�F���̐�ΓI�Ȗ@���̓����ɂ���āA���̐l�Ԃ����̎��܂łɔƂ����@���ᔽ�ɉ����āA��������Ƃ��̏d���Ɠ����d���ׂ̉�w�������ƂɂȂ�̂ł��B�ƂȂ�A
���ꂾ���ׂ̉������炦�邱�Ƃ��o�����̂�����A�������菜�����Ƃ��o����̂������̂͂��ł��B�܂舫�����ƁA���邢�͊Ԉ�������Ƃ��������̃G�l���M�[�𐳂����g���A��������ʂ�ɂ��邱�Ƃ��o����͂��ł��B
���������̐l�������ɂ܂��������_�Ň������͊Ԉ���Ă����B��蒼�����B���̂��߂ɂǂ�Ȑӂ߂��Ă��Ō�܂ŐӔC��S�����悤���Ɗo������߂Ă�����A�s�K���ڂ݂̂����ɓE�ݎ�邱�Ƃ��o���Ă����͂��ł��B
�Ƃ��낪�l�ԂƂ����̂́A���n�Ɋׂ�Ƃ��Ƒ��Ȏ�i�ɏo�悤�Ƃ�����̂ł��B���ꂪ���Ԃ�傫�����Ă��܂��̂ł��B�����Ő_�o�I�ɎQ���Ă��܂��Đ���Ȕ��f�͂������Ă����܂��B���ɂ̓m�C���[�[�C���ƂȂ�A�����Ŏ�����������Ȃ��Ȃ�܂��B���̓X�^�[�g�̎��_�̐S�\���ɂ������̂ł��v
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�������A�ō�����̂����t�ł��ˁB
�u�O�A�˕��v�ɂ͕����k�Ƃ��āA���������Ƃɑ����т��錾����Ă���킯�ł�����A�ǂ̂悤�Ȃ��Ƃ��N���낤�Ƃ��A�������m�肷��͂��Ȃǂ��蓾�܂���B
�ł�����A���V���e�^�҂́u�������e�q�͕����̓V��@�̌h�i�ȐM�k�ŁA���ɑ��鋰�|�͂���܂���B�������������Ƃ��Ƃ͍l���Ă��܂���v�Ƃ����v�����݂́A���S�ɊԈႢ�ł��B
�u�R���̕W��v�Œn���ɂ��Ď��グ�܂������A�։��]���́u�n���E��S�E�{���E�C���E�l�ԁE�V��v���o�߂���Ƃ���܂��B���V���e�^�҂́A����͎��Ȃ��ɍς݂܂������A���̐��́A������x�l�Ԃ�����ۏȂǂ���܂���B
�ꍇ�ɂ���Ă͐e�E���̑�߂�Ƃ����������ꂸ�A�l�X�l�����킹��ƁA���͒n���E��S�E�{���Ƃ����A������O����ɐ��܂�ς��\��������Ȃ��傫���A�����l�Ԃɐ��܂�ς������炵�����V���e�^�҂́u�Ȃ�Ƃ̂ȁv�ƌ��킴��܂���B
�]���́A�����p���N����������܂��A�������菞���āA�C�s���Ȃ����Ē��������ƁA�S����F���Ă���܂��B
2023�N�@�u7���̕W��v
�@�������s��
�\�\�\ �ŏ��_
����́u�����i�͂��Ղ��j�����ǂ��@�������v�Ɠǂ݂܂��B
�@���B�ɂ́A�l�Ƃ��Đ����Ă�����ŁA���낢��ȍ������P���������Ă��܂����A����ɗ��������A�ς����ς��A�E�ѓ��E�тȂ���A����������ł����܂��B
�@�����̍�����A�ǂ��Q�����ɗႦ�A���̋��̕��ɓ����Ă��A�����ē����邱�Ƃ̂Ȃ��m�ł���p���u�����ǂ��������v�Ƃ������Ƃł��B
�@
�����Ƃ́A���́A�ȉ��̂悤�Ȕ���ނ̕��Ƃ������Ƃł��B
�@�u���i��j�E�_�i��j�E�́i���傤�j�E�y�i�炭�j�v
�@�u���i�����j�E�ʁi���j�E昁i���j�E��i���j�v
��(�����◘�v�Ȃǂ̂���)�A�_(�J�߂��邱��)�A��(�̂����邱��)�A�y(�y�������Ƃ�y�Ȃ���)�A��
�u�l�̗ǂ����v
��(�����邱��)�A��(�������邱��)�A�(��������邱��)�A��(�ꂵ������)�A��
�u�l�̈������v�Ƃ��Ƃ����܂��B
�����Ƃ́A��������ς���ƁA�l�Ԃ̗~(�ϔY)��\���Ă���̂�������܂���B
�h�����Ȃ肽���~�h�Ɓh�����Ȃ肽���Ȃ��~�h
�N������Ȃ菬�Ȃ莝���Ă���~(�ϔY)���Ǝv���܂��B
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�����ŁA�ˑR�ł����A
�F����ATwitter���Ȃ����Ă�����ł��傤���H�@���͍ŋ߂܂ŗ��p���Ă���܂������A���̓x�A��߂܂����B
�����ł͐V�����Ƃ��Ă��Ȃ��̂ŁA��{�I�ɁA�j���[�X�̓e���r���l�b�g�Ń`�F�b�N���Ă��܂��B
Yahoo News�̓R�����g���̂��Ă��郂�m�������A�F���j���[�X�ɑ��āA�ǂ̂悤�Ȃ��ӌ��������Ă���̂��m�邱�Ƃ́A�Q�l�ɂȂ�܂����A�����g���R�����g����������A�ǂ肵�Ă��܂������A��������A���邱�Ƃ����������ŁA�R�����g���邱�Ƃ���߂Ă��܂��܂����B
������ԓ��ɃT�C�g��A�v���𗘗p�������[�U�[���A�N�e�B�u���[�U�[�Ƃ��������ł����A���{�����̃A�N�e�B�u���[�U�[��(MAU)�́A�����悻�ALINE��9400���ATwitter4500�� �Ȃ̂������ł��B
���{�̐l���͖�P��2450���l�ł�����A���悻36���̕���Twitter���[�U�[�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B
Yahoo! JAPAN�̌��ԃA�N�e�B�u���[�U�[�́A8400���l�������ł��B���{�̃C���^�[�l�b�g���p�Ґ�����1���l�Ȃ̂ŁA���{�̃C���^�[�l�b�g���p�҂�8���ȏオYahoo! JAPAN�ɃA�N�Z�X���Ă���v�Z�ɂȂ�܂��B
�ŋ߂�Twitter�́A�^�{�Ɣᔻ��F�Ő���オ���Ă���A���̓_�ł͎��������ł��̂ŋ^��Ɏv�����Ƃ͂Ȃ������̂ł����AG7���n�܂�A�[�����X�L�[�哝�̂������Ȃ������Ƃ��ɁA�ȉ��̂悤�ȃc�C�[�g�����āA���肵�Ă��܂��܂����B
������iA����j���哝�̂̕����𝈝����āu�����v�����ǁ@�����ɐ������ĊT�O�͖����́H�@�����̎�]�Ɖ��ˁH�@�ǂ�����ȃ��t�ȕ����ŗ�����ˁH�v
����A����́A���E�N���C�i���ǂ̂悤�ȏɂ���̂����炭�������Ȃ��̂ł��傤�ˁB
BS World News�ł͊e���̌���������News���������Ă��܂�����A����C��������ǂ̂悤�ɍ�����Ԃ�������܂��B�@
�����̍����R���I�ɐN������A��ɐ퓬��Ԃɂ���A���⍑�������˂Ȃ�Ȃ��ӔC�҂������Ȃǂ��ė������̂ł��傤���H�@�`����ɂ͑S���A�v������A�z���͂̂�������Ȃ��̂ł��傤�B
�܂��A�`����قNjɒ[�łȂ��ɂ��Ă��A�F�l�̃c�C�[�g��ǂ�ł��āu��˒[��c�v�Ƃ������t��������ł��܂����B
�v�́A�낭�ɂ��̂��ƂɊS���m�����Ȃ��ғ��m���A���ӔC�Ȃ�����ׂ���J��L����ꏊ�Ƃ������Ƃł��B
�܂���SNS�͔������������ԏꏊ�Ƃ�������Ǝv���܂��B
�@�u���t�R�������o�����R�v�Ƃ����L���������܂������A
https://tagenki.blog.jp/archives/13901276.html
�u���{���ǂ߂Ȃ��E�ǂ܂Ȃ��A���삪�����قǂɋ����A���������`���Ǝv������ł���A�i�݂��������A
�u�����ˁv�~�����̂Ȃ肷�܂��i���F�~���̂��炪�����j�A�N�����t�R�����Ă���̂��\�[�X���͂����肵�Ȃ��v
���ꂪ���t�R�����A�ƌ����Ă���̂ł����A�����S�����̎w�E�ɂ͓����ł��B
���I�ɂ́A��L�̌����͂��̓������ɂ���Ǝv���Ă��܂��B��˒[��c�ł�����A���݂��̊���f���������Ă���̂ŁA���̌��t�ɂ́A�܂��������̐ӔC�������Ǝv���̂ł����A���S�ɓ����Ȃ̂ŁA�܂��Ɍ�����������̐��E�ɂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B
�@���̂����̂g�o�́A���݂��̗쐫�̌����ڎw���āA�����X�V�𑱂��Ă��܂��B
�u���炻�������`�v�A�Ƃ��u���`�v�Ǝv���̂͂����R�ł����A���̂悤�ȕ���������ƁA����A�����������Ƃɂ��C�������A�n����ȂǂɂȂ��āA�Ђ����y�ڂ����݂ɂ��Ȃ肩�˂܂���B�i���ہA�������n�Ȃǂ��������l�������E���E�����Ă��܂��j
�쐫�̌����ڎw���A���̐����C�s�̏�Ǝv���Ȃ���A���݂��ɐ����������Ă������Ƃ͔��ɑ厖�Ȃ��Ƃ��ƐM���Ă��܂��B
���̂悤�ȖړI�̂��߂ɂ́ASNS�Ƃ�����́u�S�Q�����Ĉꗘ�Ȃ��v�ƌ����Ă͌����߂��ł��傤���H
A����̂悤�ɁA�����߂ɁA���ӔC�ɐl�𝈝�����悤�Ȑl���A����ǂ̂悤�ɂȂ�̂��e�Ղɑz�����ł��܂��̂ŁA�Ȃ�Ƃ��S�����߂Ē��������ƋF�邵������܂���B
�ł��̂ŁA���ꂼ�ꂪ���M�҂Ƃ��Ă̐ӔC�������Ă��Ȃ��A���ꗬ�������̌��t��ǂ݂ɍs���͖̂{���Ɏ��Ԃ̖��ʂƎv���܂����B
���́u�������s���v�̂��ƂɁu�V�ӌ��v������T�������܂��B
�u���������ǂ��������@�V�Ӂi�Ă��j�̌��v�Ɠǂ݂܂����A���́u���v�́A�Ԃ�Ȃ�������\���Ă��܂��B�u�ǂ�ȕ�(�ϔY)�ɎN����悤�ƁA�����^�������ɓ˂��i�ݎ������������ȁv�Ƃ����Ӗ��ł��B
�����ASNS����邱�Ƃɂ���āA���̏ꏊ��������Ȃ��Ȃ�����A�����~�܂��Ď�������܂��傤�B�u���v�͍��_�ɂ��������A�������Ă��܂����Ǝv���Ă��A�K���A�i�^�̏�ɋP���Ă��܂�����E�E�E
2023�N�@�u6���̕W��v
Dance with wolves
�_���X�E�E�B�Y�E�E���u�Y
�\�\�\ �}�C�P���E�u���C�N
�������w�����������a30�N��A�ȉ��̂悤�ȁA�A�����J�Ő��삳�ꂽ�e���r�ԑg������Ă��܂����B
�w���������`���`���A�X�[�p�[�}���A�������b�V�[�A�A�j�[��e���Ƃ�A���[���E�����W���[�A���[�n�C�h�A�����~�[�q��A�{�i���U�xetc.
��͂萼���������������悤�Ɏv���܂����A���̒��œo�ꂷ��C���f�B�A���i�l�C�e�B�u�A�����J���j�́A�قڈ��҈����ŁA�A�p�b�`���Ȃǂ́A�����m�̑㖼���̂悤�ł����B
�R�����͑P�ŁA�C���f�B�A���͈��Ƃ����̂���O��ɂȂ��Ă��܂�������A�q���S�ɁA�C���f�B�A���͎c���ŁA���낵�����݂Ƃ������ɋL���ɟ��݂��Ă���܂����B
�ł�����A10�N�قǑO�A�w�Ñ��͌��\�V���o�[�o�[�`�̗�P���x�Ƃ����{�����߂Ď�Ɏ�������A�`���̃y�[�W�ɃC���f�B�A���̎p�������V���o�[�o�[�`�̐S��G�悪�ڂ��Ă����̂ł����A�������̎��́A�q���̍�����̃C���[�W����A���́A�����삪�C���f�B�A���̎p�Ȃ̂��A�قƂ�ǂ��̈Ӗ����킩��܂���ł����B
����A�f��h Dance with wolves�h���ςāA�l�C�e�B�u�A�����J���̗쐫�̍����ɐڂ��A����Ɛ[���S����[���ł����悤�Ɏv���܂��B
���ɂ��Ďv���A���X�A�嗤�ɂ͌��Z�������āA�����֊O����N�����Ă����̂����l�Ȃ̂ł�����A���̂��Ƃ͑�O��Ƃ��āA�Y��Ă͂����Ȃ��Ǝv���܂��B
�hDance with wolves�h�@�u����̊T�v�v
1863�N�H�A��k�푈�̍Œ��A�k�R�̒��тł������W�����E�_���o�[�́A�풆�ɌR���������A���Ԃ�Ƃ��Ď��R�ɋΖ��n��I�Ԍ�����^�����A�T�E�X�_�R�^�B�̃Z�b�W�E�B�b�N�Ԃւ̕��C�i�B���n������̍r��ƍr��ʂĂ��u�ԁv�Ŏ��������̐������n�߂��B
�J��ƐH���A�����Ĉ��n�̃V�X�R�Ɓu�g�D�[�E�\�b�N�X�i2�̌C���j�v�Ɩ��t�����T�ƋY��鐶���������Ă���Ȃ��ŁA�X�[���̃C���f�B�A���B�Ƃ̌𗬂����܂��B
�����A���܂��������Ŗڂ��o�܂����_���o�[���O�ɏo�Ă݂�Ƃ����ɂ̓o�b�t�@���[�̑�Q���Q��𐬂��Ĉړ����Ă����B�o�b�t�@���[�̓X�[���ɂƂ��Ė��̗Ƃł���B�_���o�[�͋}���ŃX�[���ɕB�����X�[���Ƌ��Ɏ��ɏo���B�_���ȋV���ł�����X�[���̎��ɎQ�����钆�ŁA�_���o�[�͎����Ƃ͂ǂ�ȑ��݂ł��邩�Ƃ������Ƃɖڊo�߂Ă����B
�܂��A�c������A�X�[���ƓG����|�[�j�[���ɉƑ����E���ꓦ�����т��Ƃ�����X�[���ɏE����Ă�ꂽ���l�����Ƃ����݂��Ɉ�����ԕ��ɂȂ�A�����Č������邱�ƂɂȂ�B
�₪�ē~���������A�R�Ă肷�邽�߂ɏW�����ړ�������������B�������A�_���o�[�̓X�[���̑����𔒐l�ɒm���Ȃ��悤�A���X�̏o�����������ɋL�^�������L�����ɂЂƂ�Z�b�W�E�B�b�N�Ԃɖ߂����B�Ƃ��낪�Ԃɂ͊��ɁA���Ď��炪���������R�������勓���Ă���A�C���f�B�A���̕�����g�ɓZ���Ă����_���o�[�͕ߗ��ƂȂ��Ă��܂��B�R�����̓_���o�[�t�҂Ƃ��ď��Y��鍐����B
�Ȃ��Ȃ��A���ė��Ȃ��_���o�[�̐g���Ă����X�[���̐�m�������_���o�[��{������ƁA�ނ��쑗����n�Ԃ��B��P�U�����d�|���A�_���o�[�̖��͋~��ꂽ�B
�������A�C���f�B�A���̑�ʋs�E��ژ_�ލ��O���R�͖ڑO�܂Ŕ����Ă����B����ȏ㒇�Ԃ����ɖ��f��������킯�ɂ͂����Ȃ��Ɗ������_���o�[�́A�X�[�������ɕʂ�������A������Ȃ��Đ�R�̉��[���ւƕ��������Ă������B
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
���̉f��̊ēA����A�剉���R�T�i�I�I�I�j�̃P�r���E�R�X�i�[���߂Ă��܂��B�P�r���E�R�X�i�[��1955�N�A�J���t�H���j�A�B�����E�b�h�ɐ��܂�܂������A�����Ƃ��Ă̓`�F���L�[���C���f�B�A���A�h�C�c�A�A�C�������h�̍����Ƃ̂��ƂŁA���炭�A�ގ��g�̉ߋ�������c�̌����A���̍�i����|�������`�x�[�V�����ɂȂ��Ă���̂͋^���̂Ȃ����ƂƁA���@���Ă��܂��B
���̉f��́A��Z�����ł���C���f�B�A�����s�E���A�o�b�t�@���[���Ő��O�ɒǂ���������l���S��`�̃A�����J�Љ�ɑ��Čx����炷�Ƃ����_�ŁA�]���̐������Ƃ͑傫��������悵�Ă��܂��B
1990�N11���ɉf�悪���J�����ƁA�����g�b�v�X�^�[�ł������R�X�i�[�̏��ē�i�ł���Ƃ����b�萫��A�C���f�B�A�������Ɠ����������l�̎��_���瓖���̃A�����J�Љ��ᔻ����Ƃ����a�V�ȃX�g�[���[�A����ɑs��ȃX�P�[���ƃ_�C�i�~�b�N���@�ׂȉ��o����]�ƁE�ϏO�o���̐��ȏ^���l���B��63��A�J�f�~�[�܂Ƒ�48��S�[���f���O���[�u�܂̍�i�܂Ɗē܂��_�u����܂��܂����B
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�A�����J�C���f�B�A���̗쐫�̍����ɂ��āA�Ȍ��ɕ\�����ꂽ�u���O������܂����̂ŁA���Љ�܂��B
https://www.spiritualfriends.work/entry/spiritual-truth/teaching-of-the-america-indian
�A�����J�C���f�B�A���Ƃ����Ă����S���̕���������܂��B���`�����鋳�P�́u�����L�v�Œm���A�A�����J�ɂ����鎩�R�ی슈���̐��҂ł�����A�[�l�X�g�E�V�[�g���i1860-1946�j���u�ō��̃A�����J�C���f�B�A���̍ō��̋����v�����b�g�[�Ƀi�o�z����X�[���ȂNj�̕����̋��������A�W�����̂ł��B
�u�A�����J�C���f�B�A���̕s���̍��v
�@��\�҂��I���E�ɖڊo�߂��l�̔w��ɂ́A���ăA�����J�C���f�B�A���Ƃ��Ēn��l���𑗂����삪�l���������A�����Ă��邱�Ƃ���������܂��B�C�M���X�l��\�҃G�X�e���E���o�[�c�ɂ̓��b�h�E�N���E�h�A�O���C�X�E�N�b�N�ɂ̓z���C�g�C�[�O���A���[���X�E�o�[�o�l���ɂ̓V���o�[�o�[�`�����Ƃ�����I�K�C�h�ispirit guide�j�����܂����B
�@�A�����J�C���f�B�A���͕����̒��ɗ�o�҂����āA��E�����烁�b�Z�[�W����邱�ƂŊm���ȗ�I�m�����X�p���A�l���̓�����ׂƂ��Ă��܂����B
�@�����̒��ŁA�ނ�͂��݂��������������Ƃ���������ɂ��܂����B�ނ�̐l���̐����̊�́u�ǂꂾ�����Ԃɑ��Ė𗧂��Ƃ����Ă�����ꂽ���v�Ȃ̂ł��B
�@���a�ɐS�L���Ȑ����𑗂��Ă����A�����J�C���f�B�A���ł������A�R�����u�X�ɂ��嗤������A���m�l�ɂ�葽���̕������x�X��s�E�ɍ����A�̒n��D���A�L���X�g���ɉ��@�𔗂���Ȃljߍ��ȗ��j�ɋs�����Ă��܂����B
�@�����������Ȃ镐�͂�e�����A�����J�C���f�B�A���̗�I�Ȗ{�����~�߂邱�Ƃ͂ł��܂���ł����B�L���ȗ쐫���g�����ނ�́A�n��Љ�ւ̗�I�m�����y�̎g����тсA��l�ł������l����I�Ɋo���������ł���悤�����Ă���̂ł��B
���ɁA�ނ炪��ɂ��Ă����U�̗�I���P�����`�����܂��B�@
�u�A�����J�C���f�B�A���̐l���P�v
�@���ӁF���ւ̋��|�����Ȃ��̐S�ɏZ�݂��܂Ȃ��悤�Ȑ�������S�|���Ȃ����B�������H�ו�������A�������т������邱�Ƃ��ł��邱�ƂɊ��ӂ��Ȃ����B
�A�s�ł̍��F���̐�����������ǂ��ɂ����̂��͒N�ɂ��킩��܂���B���������悢�掀�����K�ꂽ��A���ꂩ�玟�̐����̏�i��ł����̂��Ƃ������Ƃ�m���Ă����ׂ��ł��B���|�S���������A���c�������Ƃ�������Ă͂����܂���B�^����ꂽ����̍˔\�Ɛ���̒��ōőP��s�������Ƃ������o�A�����Ď���̐��E�ł̋����͒n��ł̏��Ƃɂ���Č��܂�Ƃ����F���������ĕ��������邱�Ƃł��B�V���ɂ͖����̊E�w�i���U�j������A����̐��E�ł��ǂ���Ƃ���́A�e���̗�I�����x�ɂ���ĈقȂ�܂��B�쐫�̍����i�����̐[���j�ɔ�Ⴕ�āA������ϔ������Ȃ�܂��B�S�D�����l�B����炷�Ƃ���ɁA���ȐS���������l�͐�ɓ��荞�߂܂���B�V���ł͗�I�Ɍ��シ��ɂ�āA����܂ł̊E�w�����Ƃɂ��Ă�荂���E�w�ւƐi�݂܂��B
�B�v�����F�����̉e���͂̋y�Ԕ͈͂̐l�X�ɑ��Ă͂������ߐ[���C������Y��Ă͂Ȃ�܂���B�カ�ҁA�a�߂�ҁA�V�����҂̐��b�����邱�Ƃ����A��ɗ��҂̓w�߂ł��B
�C�h�ӁF�S�Ă̐l�Ɍh�ӂ�����Ȃ����B�������A�����Ȃ�҂ɂ��ڋ��ɂւ艺���Ă͂����܂���B�^����������^���邱�Ƃ̕������_�Ȃ��Ƃł��B
��I���݂ł��鎄�B�̍��́u�_�����_�̐����v��ттĂ��܂��B��I���݂ł��邩�炱���A���B�͖����̉\�����߂Ă��܂��B���E����炸�������Ƃ��Ƃ�M���邱�ƂŁA���̉\�����ő���Ɉ����o���܂��B
�D�_�Ƃ́F�_�Ƃ͉i���̑��݂ł���A�`�̂��������A�S�m�ɂ��đS�\�ł���A����ŕ`�ʂ��邱�Ƃ̂ł��Ȃ����݂ł��B��������̂��_�̒��ɑ��݂��A�_��ʂ��Ċ������܂��B��X�̐��q�S�ƒ����S�́A���̐_�Ɍ����Ȃ���Ȃ�܂���B�b�݂͑S�Đ_��艺����܂��B�䂦�Ɍh�i�Ȃ�C�����Ő_���u�����Ȃ���Ȃ�܂���B�_�͖{���I�ɂ͔�l�i�I���݂ł��B
�E�߁F�߂Ƃ͐_�̗�I�@����Ƃ����Ƃł��B�߂͂��ꎩ�炪���������炵�܂��B
�l���_��z�����A�l�Ԃ̎p�Ɏ����đz���������ł��B�������A�����J�C���f�B�A���̌��t�́A��I�Ȑ^����\���Ă��܂��B�ނ炪���߂Ă���_�ithe Great Spirit�j�́A�l�ԓI���������Ȃ������݂ł͂Ȃ��A�S�F���Ɉ��Ƃ��Ė����Ɍ������鑶�݂ł��B����͑S�����Ɋ��͂�^�����͂ł���A�i���s�ς̗�I�@���Ƃ��đS�����̂ɏ�ɓ��������Ă��܂��B
�@��I�@���Ƃ͎����̍s�������ݏo�������ʂ��A�����I�Ɏ����ɕԂ��Ă���Ƃ������̂ł��B���Ɋ�Â��s�ׂ͎���̗�I�����ƂȂ�A���ӂɊ�Â��s�ׂ͗�I��ށi�����j�ƂȂ�܂��B��I�@���͒n��ɂ��Ă��V���ɂ��Ă��S�Ă̐l�̐l���ɓK������Ă��āA�l���͊����Ƀo�����X���Ƃ���悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�@���m�l�ɂ��A�����J�C���f�B�A�����Q�͐M�̈�ɂ��y�т܂����B�q�������͊�h�w�Z�ɑS���������w�������A�e�����̌���g�p�͋֎~�̏�A�p��Ő����̈ËL�ƋF���������������܂����B
���m�Љ�ł́A��I���m�̌��͎҂Ɛ��E�҂����т������ʁA��I�@���̑��݂�����������ĎЉ�ɐ��`���s���͂��Ȃ��Ȃ�A�i���ɓn��\���R�▂�����Œm����L���X�g���ɂ��e���Ɩ\�s�̈Í�����ɓ˓����A�A�����J�C���f�B�A�������̋]���ƂȂ�܂��B
�@���̂��Ƃɗ�E���ōł��S��ɂߗ܂����͈̂���I�ɐ_�̍��ɂ܂肠����ꂽ�C�G�X���ƁA�V���o�[�o�[�`�̗�P�Ȃǂ̎O���P�͓`���Ă��܂��B�C�G�X�͖ړI�ɂ����Đ_�ƈ�ł������A�����Đ_�ł͂���܂���B�ނ͒n��ɍ~��Ă����鍰�̒��ł��ō����x���̈̑�ȗ�ł����B
�@�ނ͓����̖��O���ׂ��Ă����������S�̐������̊ԈႢ������A��I�m�������߂鐶���֗����߂点�A�A�����J�C���f�B�A�����d�v�����Ă����̂ƑS��������I�@���̑��݂������܂����B�l���~���͓̂���̏@���ւ̐M�ł͂Ȃ��A���퐶���̒��̎����̌����ɂ����Ȃ��Ɛ����A���痦�悵�Ď����̌��������H�����͔͓I�Ȑl�ł��B
�@��I�@�����瓦�ꂽ�育�܂�����l�͒N�����܂���B��I�m���͌l�ɂ����Ă��Љ�ɂ����Ă��A���a�������炷�ƂĂ���Ȍ��ł��B�@
�@��I�@�����n�m�����C�G�X��A�����J�C���f�B�A�������퐶���Ŏ��H�����悤�ɁA���B�l�ԂɂƂ��ĉi�����̂���B��̕x�͐S�̖L�����A�D�����ł��B���͂̐l�A���R�A�����A��������芪�����ׂĂɑP�ӂŐڂ���悤�S������A���ꂾ����I�ɐ������A�������ϔ��������U�֓�����A�S�͍K�����ɖ������ӂ�܂��B��I���������A�n��l���̋��ɂ̖ړI�ł��B
�Ō�ɁA�嗤�ɓ��B���A���n���C���h�Ǝv�����݁A���Z�����C���f�B�A���Ɩ��������R�����u�X�̌��t�����Љ�܂��B
�u���̒������j�����n����̂ǂ̏@���ɂ��܂��āA�A�����J�C���f�B�A���̏@���͍ō��ɏ����ł���A�n����̊T�O�͐������ɂ߂�B�i�Ղ����Ȃ���������Ȃ����т̋V�����Ȃ��A�_�ithe Great Spirit�j�Ƃ����ڂɌ�������厩�R�̎x�z�͂𐒔q���A�M�̒��ɂ����q����B�_�Ƃ͑傢�Ȃ��ł���A�����ȗ�ł��鎄�B�l�Ԃɂ������̗쐫�^���Ă���Ă���B�v
2023�N�@�u5���̕W��v
���̂��Ƃ�
�\�\�\ �w��ʟ��όo�x
�w��ʟ��όo�x�Ƃ������o�̒��ɁA�u���̂��Ƃ��v�ƌĂ����b������܂��B���̂��o�́A���߉ޗl���őO�̍Ō�̋����Ƃ���邨�o�ŁA���߉ޗl�̈⌾�Ƃ������邨�o�ł��B
�u���́A���茻�ꂽ�肷����̂Ƃ��Č����Ă��邯��ǁA�{���́A���͏�ɋ�ɂ��葱���A���ꂽ��v�����肷����̂ł͂Ȃ��B����Ɠ����悤�ɁA�u�b�_���܂��A���܂ꂽ��S���Ȃ����肷��悤�Ɍ����邯��ǁA�{���u�b�_�͐��ł�����悤�ȑ��݂ł͂Ȃ��B�����l�X�ɐ��������͕̂K���ł��邱�Ƌ����邽�߂ɁA���ςɓ���̂ł���B
�����Č��͖������茇�����肷��悤�Ɍ����邯��ǁA���͖����������Ă���킯�łȂ��A��Ɋۂ��`�����Ă���B���i�ߑ��j���l�Ƃ��Đ��܂�A�������A�����Đ^���ɖڊo�߃u�b�_�ƂȂ�A���܂��ɟ��ςɓ��낤�Ƃ��Ă���l�́A���������������Ă���悤�ł���B���������̓u�b�_�͖����������Ă���킯�łȂ��A��Ƀu�b�_�Ƃ��č݂�B�����l�X������Ƃ���ɂ���āA�����������Ă���悤�Ɍ����邾���ł���B
�܂����͒��⑺�A�R��J�A��˂�r�A�Ȃǂɂ������B�����Đl���s���Ƃ���ǂ��ɂł��������邱�Ƃ��ł���B�������ǂ��Ō����錎���������ł���B�܂��l�̌����ɂ���āA���̑召���قȂ錩���������邯��ǂ��A�����̂��̂̑傫���͈�l�ł���B�u�b�_������Ɠ����悤�ɁA���Ԃ̐l�X�݂̍���ɏ]���Č���A���鏊�ɂ��̎p��\�킷�B���i�ߑ��j�����̈�ɉ߂��Ȃ�����ǁA�u�b�_���̂��̂́A���̂悤�ɏ�ɍ݂葱���A�ς�邱�Ƃ��Ȃ����̂ł���B�v
�ƁA���̂悤�Țg���b�ł��B
�o�v�Ɩ����������J��Ԃ��悤�Ɍ����錎�ł����A���͋��̂̌�����ɉF���ɍ݂葱���邱�Ƃɂ��Ƃ��āA�ߑ��͐l�Ƃ��Đ��܂ꎀ�ɂ䂭����ǁA�u�b�_�Ƃ������ݎ��͕̂s�ρE���Ղ̂��̂ł���Ƃ������Ƃ�����q�ɓ`���Ă�����̂ł��傤�B�����ł����u�b�_�Ƃ����̂́A���̂Ȃǂ̌`��Ȃ��A���̖{���A�������̂��́i���@�j�Ƃ��ė�������Ɨǂ���������܂���B�܂�A�ߑ��S����A���͏����Ă��܂����悤�Ɍ����邩������Ȃ�����ǁA���̖{�����鋳���͂����ƍ݂葱���Ă���̂�����A���̋������˂菊�ɂ���悤�ɂƂ����A���Ƃ��ł��B
1969�N7��20���A�č��F����s�m�A�j�[���E�A�[���X�g�����O�ƃo�Y�E�I���h�������l�ގj�㏉�߂āA���ʒ����ɐ������܂����B
���̃j���[�X�ɐڂ������A���ɐl�ނ������܂ŗ������ƁA�����܂������A����ɁA�����猩���n���̉f����NASA������J���ꂽ�Ƃ��ɁA���������n���̉f�������̂悤�Ɍ����Č��������ƂɁA���t�ɕ\���Ȃ��قǂ̊��S���o���܂����B
���߉ޗl�̎��ォ��Q�T�O�O�N�߂��āA���̐��X�����p���A���߂āANASA�̉f����ʂ��Č��邱�Ƃ��ł����Ƃ������Ƃ́A�Ȃ�Ƃ����K�^�ł��傤�B
��X�̏Z��ł����n�͋��̂ł���Ƃ����O��̂��ƂŁA�N���X�g�t�@�[�E�R�����u�X�����Ɍ����čq�C���A�A�����J�嗤�ɓ��������Ƃ��ɁA���̒n���C���h�i�����͓��A�W�A�S�̂��w�����j�ƌ�����A�ȍ~�A�����J��Z���i�̑唼�j���C���f�B�A���ƌĂԂ悤�ɂȂ�܂����B
�l�Ԃ͒����������Ԃ��₵�āA����A�n�������̂ł���A�F����Ԃɕ�����ł��邱�Ƃ��ؖ����悤�Ƃ������Ă����̂ł��B
�ł�����A���́A���̌��̂��Ƃ��̂����@��ǂ��ɁA�܂��A���߉ޗl�Ɠ�������ɐ������l�X���A���̎����𐳊m�ɔc�����Ă������ƂɁA�{���ɋ����܂����B
�������́A�����ڂɂ������Ƃ��ȂǁA���u���̐��ɂ͐_�������Ȃ��v�ƌ����ĒQ�����肵�܂����A�_�����ۂ��ׂĂ̂��Ƃ́A���Ɖ��ɂ���āA�����Ă���킯�ŁA�������̑z���Ƃ͑S�����W�ɁA�݂葱���Ă���̂ł��B������̑z���ŁA����ɏ������茻�ꂽ�肷����̂ł͂���܂���B
���R�A��_���������ɓs���悭�A���ꂽ��A�������肵�Ȃ����Ƃ͎����̗��ł��B
�ł��̂ŁA��������s�^�ȏo�����������āA��_���̑��݂��^�������Ȃ����Ƃ��́A���͂��̂悤�ȏ����킹�ɂȂ��Ă���Ƃ������Ƃ��ÂɎ~�߁A����ȏ�A���Ԃ��������Ȃ��悤�ɁA�w�߂邵���Ȃ��Ǝv���܂��B
�u�_�������Ȃ��v�Ǝv�����Ƃ́A�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����Ǝv�����ƂƓ����A�Ƃ��߉ޗl�͂���������Ă���̂��Ǝv���܂��B
�܂��A���߉ޗl��C�G�X�l�͗�I�ɕʊi�ŁA������E�ɂ�������Ⴂ�܂��̂ŁA������x�A���̐��Ɍ���邱�Ƃ́A�\�z���ɂ����ł����A��X�̂悤�ȕ��ʂ̐l�Ԃ́A���ꂼ��̈��ʂ̖@������āA�`��ς��Ȃ���A���܂�ς�莀�ɕς�肵�Ă��܂��B
�g�̉��̕��ŁA��ɐ����ꂽ�����A�i���ɏ����Ă��܂�����ł͂Ȃ��A�ꎞ�A��X�̊�ɂ͌����Ȃ��Ȃ�����ԂɂȂ��Ă��邾���ł�����A���������܂������悤�ɁA�ĉ�̎�������ė��鎞���y���݂ɂ��܂��傤�B
���̂悤�ɁA�������[�܂�A�䎩�����ꎞ�A���̐���������鏇�Ԃ��������ɁA�Q�ĂȂ��ōςނƎv���܂��B
2023�N�@�u4���̕W��v
�����匠��
�\�\�\ https://nekogami.jp/
�挎�A�u�������R�����r�m�r�ʼn���v�������������Љ�܂������A���̌�A3���P���ɏ��ޑ������ꂽ�ƁATNC�e���r�����{���Ă���܂����B
�u��q���s�h�v�̋^���ŏ��ޑ������ꂽ�̂́A�����������s�ɏZ�ނP�V�̒j�q���Z���ł��B
�r�m�r�ɒj�q���Z�����Ε����R��|�����悪���e����Ă��āA��O�҂��甪���x�@���ɏ������������Ƃ�A������������e���u�����̑��q������Ă���v�Ȃǂƌx�@�ɘA�����A���o���܂����B
�����l���A�����̑��q�����ł����Ă��邱�ƂɋC�Â������́A���������ꂽ�Ǝv���܂����A�悭�x�@�ɂ��A�������������ƂƎv���܂����B
�c�Ƃ����ŁA�����u�₩�ȋC�����ɂȂ��Ă���܂������A�����R���P���ɍ�ʌ��˓c�s�̒��w�Z�Ő搶���n���Ő�t�����鎖�����N���܂����B�����āA���̎������N�������̂��A��͂�A����17�̍��Z���ƕ��A�ǂ��\�����Ă悢��番����Ȃ��قǁA�V���b�N���A���W����C�����ɂȂ�܂����B
�搶�͉���������t�����,�d�����Ȃ���A���k����������ĉ������āc
������l�Ԃ��������ŁA���̂悤�ȕ��l�̂悤�ȕ��������ŁA���t������܂���B
�����ł͘Z���։������܂����A�܂��ɂ��̐����Z���։�̏k�}�̂悤�ȗl����悵�Ă���c�Ǝ������Ă��܂��B
���̎����̂�����ƑO����A�ߗׂŔL�������A���u���鎖�����N���Ă����悤�ł����A���̌����u������������v�Ƌ��q���Ă���Ƃ̂��ƁB
�u�l���E���Ă݂��������v�Ƌ��q���Ă���悤�ł����A���̑O�ɁA�L���E���āA�o���o���ɂ��c�Ƃ��A�܂��ɑz����₷�鎖�Ԃł��B
�q���̍��A�ꂩ�炱�̂悤�Șb�������Ƃ�����܂��B��͊��n���̋��Ƃ̏o�ŁA�̂����X�����̉ƕ��������Ǝ������Ă���܂������A�����͗���������̂ɂ��܂ǂ�����A�L���g�����̂ŁA���̒��ŐQ�Ă��������Ȃ̂ł����A����������ɋC�Â����A��t���Ă��܂��L������ł��܂����Ƃ̂��ƁB���̂��ƁA��������͋�������Ȃ莵�]���|�����Ƃ����b���A�u�L���M�邩��v�Ƃ������t�Ƌ��ɁA���x����������܂����B
�����ŁA�{���Ɂu�L���M��v�̂��ɂ��āA�������Ă݂܂����B
�×��A�����L�����͊e�n�ɂ���A��O�瓇�E�v���ėL�n�Ȃǂ����ɗL���ł����A��������s�́u�����匠���v�͌䑶���������ł��傤���H
�]�ˎ���̑O���̒勝�N�ԁA�����ˉ��Α��i���E����s���Β��j�̏������s��ŁA���鑺���~�����߂ɕx���ɋ�����A���łɕԍς����ɂ�������炸�A�x���̍����Ŗ��ԍς̔G��߂𒅂����A���ӂ̓��ɕa�����܂����B
�؋��̒S�ۂɂȂ��Ă����y�n�͕x���Ɏ��グ���Ă��܂��A�����̍Ȃ̂����͕�s���ɑi���o���̂ł����A�x���ɔ������ꂽ��s�͕s���ȍق��������܂��B�����������s���Ƃ��Ĕˎ�ɒ��i�������ʁA���i�̍߂ɂ�菈�Y����Ă��܂��܂����B���̌�A�����̎����Ă����O�єL�������L�ƂȂ�A�x�����s��̉Ƃ�łڂ����Ƃ����`���ɗR�����邻���ł��B�����ɂ͑S���I�ɂ��������l�R�̍��������邻���ł��̂ŁA��x�K��Ă݂����Ǝv���Ă��܂��B
�Ƃ���ŁA�u���͐l�ɕt���A�L�͉Ƃɕt���v�Ƃ������t���������ɂȂ������Ƃ͂���܂����H�u���͐l�Ԃ�����Ă���邯��ǁA�L�͂ǂ��炩�ƌ����A�l�ԂƂ̊W�͒W���ŁA�Ԍ��Ȃ�ʔԔL�ɂ͂Ȃ�Ȃ��v�Ȃ�Ďv���Ă��܂��H
�ی�L5�C�ƕ�炵�Ă���g�Ƃ��āA�f���ł��܂����A���́A�L�̃X�s���`���A�ȃG�l���M�[�͂��Ȃ苭�͂ł��B�L�͐��܂���G�l���M�[�����m�ł���\�͂������Ă��āA�I�[�����ƂĂ������̂ŁA�l�K�e�B�u�ȃG�l���M�[���ȒP�ɒǂ��������Ƃ��ł���̂ł��B
�l�ԂɈ��e�����y�ڂ��G�l���M�[���́A�ڂɂ͌����܂��A������Ƃ���ɑ��݂��܂��B���ɂ����́A���������߂鐬�����Ă��Ȃ��l�̍������܂��Ă����肷�邱�Ƃ�����܂��B���ɔL�������A�����Ȃ���Ԃ������ƌ��߂Ă��邱�Ƃ����܂ɂ���܂��B
�J�ł́A���o�̖{���l�Y�~�ɍr�炳���̂�h�����ߔL���������Ƃ�����������A�����ɔL���t�����݂����ȃC���[�W�́A���̂悤�ȗ��R������̂��Ǝv���܂����A��I���Ƃ��Ă̖������S���Ă����ʂ�����ƐM���Ă��܂��B
�E�`�̔L�����́A���ĂĂ����ꂽ�ی�L�ł����A������A�ی삳��Ă���̂́A���₨�����Ǝ������Ă��܂��B
�@�����v���Ă����Ƃ���ŁA���̂悤�ȃl�b�g�̋L�����ڂɗ��܂�܂����B
�u���ɏP��ꂽ�j�̎q���������L�v
�A�����J�A�J���t�H���j�A�B�x�[�J�[�Y�t�B�[�����炱��ȃj���[�X���͂����B����13���i�Q�O�P�S�N�T���j�A����O��4�̒j�̎q�A�W�F���~�[�����]�ԂŗV��ł����Ƃ���A�ߏ��Ŏ����Ă��錢���˔@�P���|�������B
���̓W�F���~�[�N�������Ƃ��̂܂܃Y���Y���ƈ�������܂킻���Ƃ����B���̎��A�����悭��э���ł����̂́A�W�F���~�[�N�̉ƂŎ����Ă���L�̃^���i���X�j�B�^���͑S�g�Ō��Ƀ^�b�N������ƁA���̂܂܌���ǂ����Ă��B���̈ꕔ�n�I���Ď��J�����ɎB�e����Ă����B
�^����6�̎��l�R�ŁA2008�N����W�F���~�[�N�̉ƂŎ����Ă���B���̌��͋ߏ��Ŏ����Ă��鐶��8�J���̃`���E�`���E�ƃ��u���h�[���̍�����B�W�F���~�[�̂��ꂳ��͂��̎��A�ɐ�������Ă��āA���ѐ����čQ�Ăċ삯�t�������A�Ď��J����������܂ł͉����N���Ă��邩�킩��Ȃ������Ƃ����B
�אl�̘b�ɂ��ƁA�Ԃ��o�����ƌ��ւ̃Q�[�g���J�������Ɍ��͓��������Ƃ����B�W�F���~�[�N�͌y�x�̎��ǂ�����A�Ƃɂ͕����̊Ď��J�������ݒu����Ă����B
�W�F���~�[�N�͘r�ƕ��������䂵�����A�����^�����삯���Ă���Ȃ�����������ƂЂǂ����ƂɂȂ��Ă������낤�B�W�F���~�[�N�́A���̌�̃C���^�r���[�ŁA�u�^���̓{�N�̃q�[���[���B�v�Ɠ������������B
���ہA���̎��̗l�q�́A�ȉ��̓���Ō��邱�Ƃ��ł��܂��B
https://karapaia.com/archives/52162674.html
�@���̓�������āA���������ɂȂ�܂����B�������͂邩�ɑ̂��傫���A���ɗ����������Ă����ȂǁA�Ȃ�Ƃ��Ă��W�F���~�[�N�����˂Ƃ�����S�������̂ł��傤�B�^�������̗�i�̍����ɂ������ł��B
�@�ł��̂ŁA�L���M��Ƃ���Ȃ�A����̓`�����Ɨ��R�������Ă̂��Ƃ��Ƃ����蒸����Ǝv���܂��B
�`���ɏЉ���A�P�V�̍��Z���B�������A�L�����ɂ����s���́A�K���A�l�Ԃ̖@���ɂ���čق��������A�����Ƌ��낵�����ʂ��A�����ɕԂ��Ă��邱�ƂɂȂ�Ǝv���܂��B
�܂��A�E�`�̔L�����́A�F�A�����Ɏ̂ĂĂ����ꂽ�L�����ł��B�L�ɂ����炸�A�����Ă�����̂��̂Ă�Ƃ����s�ׂ́A�s�҂Ɠ����ŁA�ƍ߂ł��B���̏ꍇ���A�K���͂���܂��̂ŁA�����Ă�����̂��������Ƃ������Ƃ͐�ɂ�߂Ē��������ƁA�ɂ��肢�v���܂��B
2023�N�@�u3���̕W��v
�����͂������Ƃ̔@���ɏ]���Ă����ނ�
�P�ƈ��Ƃ̕���ł��낤
�����s���������l�X�͒n���ɂ����ނ�
�P�����Ƃ������l�X�͓V�ɐ��܂��ł��낤
�\�\�\ �u�b�_�w�����̂��Ƃx��P�͂Q�R�C�Q�S
2���P���ɔz�M���ꂽ�j���[�X�����āA���t�������܂����B
�u��������Ȉ��ӂ����@�������R�����r�m�r�ʼn���v
https://www.youtube.com/watch?v=_QHYYVZrYNs
�Èł̒��ŁA�Ⴂ�j�����������x���R�����Ă��܂��B
�����������S�L�쒬�ɂ���\�O�̕����J�����u�\�O�Łv�ŋN������������ȍs�ׂ��r�m�r�Ŋg�U����܂����B
�ɂ݂������~��A�ۂ�����Ƌ����́A�Èł̒��ɓ����Ă����Ƌ�Ԃ�����܂��B�\�O�̂̕��������J�肵�Ă���A���̓��̐��̂��R��ꂽ��|���ꂽ�肵�܂����B
�|���ꂽ�����͊��Ɍ��ɖ߂���Ă��܂����A�e�n�Ő��|�����Ȃǂ��s���Ă���YouTube�`�����l���u���|�n�S��z�M�sDanger Patrol�tKeimaro�v�ɂP���A���̓��悪���A�r�m�r�Ŕ��M����Ɗg�U���A���̐����������܂����B
���n�̓l�b�g��Łg�S��X�|�b�g�h�Ƃ��ďЉ��n�߂Ă��狻���{�ʂŖK���l�������A���ɂ͎ԂɎ~�߂��ςȂ��ɂ�����A�߂��̏Z�l�̕~�n�ɏ���Ɏ~�߂���ƃ}�i�[�ᔽ�҂������Ƃ����܂��B
�܂�����̂悤�Ȃ�������Ȃǂ����Ƃ�₽�Ȃ������ł��B
�t�߂̏Z�����A�������f���Ă���l�q�ŁA�x�@������̍s�ׂ�c�����Ă��āA�함�����̉\��������Ƃ݂ďڂ����o�܂ׂĂ��邻���ł��B
�m���Ƃ��Ă̎��̗��ꂩ��݂āA�S��X�|�b�g�ƂȂ��Ă���悤�ȏꏊ�ŁA���̂悤�ɖ��@�ȍs�ׂ��s����Ƃ������Ǝ��̂ɁA�|��������܂��B
���̓���ɑ��āA��R�̃R�����g�����Ă��܂������A���̓��̂����������Љ�����Ǝv���܂��B
�P�C����͈��Y�ł͂Ȃ��ƍ߂ł���B��̂������Ȃ̂ŁA�ƍ߂̏؋����摜�Ŏc���Ă��܂����A�ߊl���Č�����^���u��������v�Ƃ͂����������Ƃ��Ƌ����Ă��Ȃ��ƁB
�Q�C��]���i�̌��������ǁA�����̍D������A���R�ɂ�肽���Ă����������Ƃ���ƁA���x�͂ǂ�ǂ�K�����o���Ď��R���Ȃ��Ȃ邯�ǁA�����Ŏ����̎���߂Ă���́A�킩���ĂȂ��Ȃ��B
�R�C�R������ɒj�̌��ɉ������������͎̂��������ȁH���Ȃ肨�{��̗l�q�ł������B
�����������Ƃ����F�肵�܂��B
�S�C���̔�������N�ɏd���V�����B���̐��̒��A���H�X�ɂ��Ă��y���C�����ł������炶��ς܂���Ȃ��B���{�l�̐S�������Ȃ����B
�ƁA���̂悤�Ɂu��������v�Ƃ����ӌ������������̂ŁA���̒��܂��̂Ă����̂ł͂Ȃ��ƁA�����~��ꂽ�C���v���܂������A�ȉ��̂悤�Ɂu�n���v�Ɍ��y���ċ���������܂����B
�T�C�Z���̒��ōł��ꂵ���n���E�s������B
�U�C�c�O�Ȃ���ނ͑����̕��鎖�ɂȂ邾�낤�ˁB���g�Ȃ��s�ׂ͌܋t�߂̈�A������Ȃ��B
�����͖��Ԓn���s���B�Ƃ͜������Ă������邱�Ƃ͖����B
�����ǂ�ʼn������Ă���A�i�^�A�u�n���v���Ă���Ǝv���܂����H
���͎��A���ۂɒn���֍s�����������̂��b���f�������Ƃ�����̂ł��B
�����A20�N�ȏ���O�̂��Ƃł����A����f�C�T�[�r�X�̎{�݂ŌX���{�����e�B�A�������Ē��������̂��Ƃł��B
�V�O�キ�炢�ɂ��������j���ł����A�]�[�ǂœ|����A���̎{�݂𗘗p����Ă��܂����B
�s���R�ɂȂ�ꂽ����ŁA���ɘb�������ė���ꂽ�̂ł��B
����ɂ��܂��ƁA�]�[�ǂ̔�����������Ĉӎ����Ȃ��Ȃ������A�ꐶ�����A����j���ł��邱�ƂɋC�����܂����B�����ɓ����݂��Ă��āA����Ƃ̂��Ƃł��ǂ蒅���A�㗤���悤�Ƃ����Ƃ��A�ԋS�A�S�Ȃǂ�����āu�܂��A���O�͂����ɗ���̂͑����v�ƌ���ꂽ�����ł��B���݂����A�Y�u�Y�u�Ɛ�̒��ɒ��߂��A�u���[�b�v�Ƌ���ŁA���ڂꂩ�����Ƃ��ɁA�͂��ƁA�ӎ������߂��������ł��B
���̒j���Ɂu�n�����Ė{���ɂ���̂ł����H�v�ƕ�����܂����̂ŁA�u�ӎ����߂��ėǂ������ł��ˁv�Ɛ\���グ�܂����B
�����āA�u�n���s�ɂȂ�悤�ȐS�����肪����̂ł����H�v�Ƃ���������ƁA�Â��ɂ��Ȃ����ꂽ�̂ł����B
���̒j���́A�䎩���̉������������̂��A���̎��͂��łɋC�Â��Ă����āA��������߂Ď�������b������A�S����������߂Ă������������̂ŁA���̌�͖{���m�̒n���ɍs���Ȃ������ƐM���Ă���܂��B
�����ł́A�����Ƃ���������̂́u�n���E��S�E�{���E�C���E�l�ԁE�V��v���o�߂���Ƃ����Z���։������܂��B���̂����̒n���́u��ŔM�E�ŔM�E�勩���E�����E�O���E����E�����v��7�̒n�����d�w���Ă���Ƃ����܂��B
������l�A�n���̂��b�����ĉ��������̂́A�E�`�̒h�Ƃ̕��ł����B���̕��́A����21�N�ɖS���Ȃ�ꂽ�̂ł����A�����̂��Q��Ɏf���Ă���܂������鎞�A�u����l�A���͐���A����̐��E��S�Č����Ē������Ƃ��ł��܂����B�Y��Ă͂����Ȃ��Ǝv���A�G�ɕ`���Ă݂܂����B�v�Ƃ��������A���̊G�������Ē����ƁA�܂��ɋɊy����n���܂ł̗l�q���`����Ă���܂����B
�n���́A�����̐��E�B���������悤�ȈŁB���̒��ɁA�l�Ԃ̎�Ǝv�������̂��A�S���S���ƕ`����Ă���܂����B���̈Èł����A������j�̎R��A���̒r�n�������A�����Ƃ����Ɛ[�����낵�����̂ł����B
�ԋS�A�S�Ȃǂ���������Ă����n���́A�܂��A�܂��ȕ��ŁA�{���̓ޗ��̒�Ƃ����̂́A�����Ȃ��A�N�����Ȃ��A�W���W���Ƃ����^���ÂȐ��E�ŁA�����̎��ȐS�ƌ������������Ȃ����|�̐��E�ł��B
���̒��ŁA��X�Ƃ��邤���ɁA���ӂ̔O�Ɋ������˂āA
�u�{���ɂ��߂�Ȃ����B�ǂ����������������B�������������B�v�ƐS����̋��т������A�V�ォ���̋~���̌����~��Ă��邻���ł��B
�����́A�`���̂悤�Ȏ����݂̂Ȃ炸�A�A�������E�l�����̂悤�ȁA�����ƍ߂����܂�ɂ��������鐢�̒��ɂȂ��Ă��܂��܂����B
���ہA�Ɋy���A�n���ɍs���l�������肪�������āA�n���̔Ԑl����Z���̂悤�ł��B
�Ȃ�Ƃ����āA�n���S�̗̂�I���x���������Ă����Ȃ��ƁA�܂��܂��A������ԂɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����ƐS����뜜���Ă���܂��B
2023�N�@�u2���̕W��v
�O��̕���
�\�\�\ �@�p�[�����x���o�T
�u���̐��ɂ͎O��̐l������B��ɍ������̂悤�Ȑl�ƁA���ɏ����������̂悤�Ȑl�ƁA���ɏ����������̂悤�Ȑl�ł���B
�@�@��ɍ������̂悤�Ȑl�Ƃ́A�����Ε��𗧂ĂāA���̓{��������A�{�肪�A���ݍ������̂悤�ɏ����邱�Ƃ̂Ȃ��l�������B
���ɏ����������̂悤�Ȑl�Ƃ́A�����Ε��𗧂Ă邪�A���̓{�肪�A���ɏ����������̂悤�ɁA���₩�ɏ�������l�������B
���ɏ����������̂悤�Ȑl�Ƃ́A���̏�ɕ����������Ă��A����Č`�ɂȂ�Ȃ��悤�ɁA���l�̈�����s���Ȍ��t���Ă��A�������S�ɐՂ𗯂߂邱�Ƃ��Ȃ��A���a�ȋC�̖����Ă���l�̂��Ƃ������B�v
�{��͐l�Ԃ����ʂɎ�����ł���A�{��ׂ������ɑ��ē{��͓̂�����O�̂��Ƃ��Ǝv���Ă��܂��B
�����A���̈���ŁA�{��̊���͐S�g���ɏ��Ȃ��炸���e�����y�ڂ��܂�����A�{����R���g���[���o����A����ɉz�������Ƃ͂���܂���B
���̎O��̕�����栂��ł́A�{��ɑ��Đl�Ԃ̃��f�����R����Ă��܂��B
��ɍ������̂悤�Ȑl�Ƃ́A�{�肪�����Ȃ��l�̂��ƁA���ɏ����������̂悤�Ȑl�Ƃ́A�{���Ă��{�肪���₩�ɏ�����l�A���ɏ����������̂悤�Ȑl�Ƃ́A���������{�邱�Ƃ̂Ȃ��l�̂��Ƃł��B
�Q�O�P�Q�N�P�O���̕W��ŁA
�u�{����̂Ă�@���S����������@�����Ȃ鑩���������z����
���̂ƌ`�ԂƂɂ�����炸�@���ꕨ�ƂȂ����҂́@��Y�ɒǂ��邱�Ƃ��Ȃ��v
�@�i�@��o�i�_���}�p�_�j��P�V�́@�{��@�Q�Q�P�j
�Ƃ������߉ޗl�̂����t�����Љ�܂������A�����I�ɂ́A���ꂪ�u�{��v�ɂ��Ă̊�{�I����ł��B
1970�N��ɃA�����J�ŁA�{��̊���Ə��ɕt���������߂̐S������A�S���g���[�j���O�Ƃ��ăA���K�[�}�l�W�����g�����܂�܂����B
�{��Ȃ����Ƃ�ړI�Ƃ���̂ł͂Ȃ��A�{��K�v�̂��邱�Ƃ͏��ɓ{������ŁA�{��K�v�̂Ȃ����Ƃ͓{��Ȃ��čςނ悤�ɂȂ邱�Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă��܂��B
�A���K�[�}�l�W�����g�́A�Ⴂ������A�l�ԊW��ǂ�����S���g���[�j���O�ł��B
�A���K�[�}�l�W�����g�Ƃ́A����Ɓu�{��̊Ǘ����@�v�ƂȂ�܂��B�����͔ƍߎ҂̂��߂̋����v���O�����ȂǂƂ��Ċ��p����Ă��܂������A����Ƌ��Ɉ�ʉ�����A��Ƃ̌��C�Ȃǂɂ����������悤�ɂȂ�܂����B
�l�͎���������܂ő厖�ɂ��Ă������l�ς◝�z�𗠐�ꂽ�Ƃ��ɓ{��܂��B�s����s���Ȃǂ̃}�C�i�X�̊����v�����K�X�̂悤�ɗ��܂��Ă���ƁA�����̒��ɂ������u�������ׂ��v�Ƃ������z�≿�l�ς�����ꂽ�Ƃ��ɁA���X�C�b�`������܂��B�����ă}�C�i�X�̊�����܂��Ă���قǁA�{��̉����傫���R���オ���Ă��܂��̂ł��B
�u�������ׂ��v�Ƃ��������������ƁA�}�C�i�X�̊���E��Ԃ�2�����낤���Ƃœ{��͔������܂��̂ŁA
�t�ɁA�ǂ��炩�����炷�����ł��A�{������������邱�Ƃ��ł���ƌ�����Ǝv���܂��B
����ŁA�{��ɂ͂����ЂƂA���ݓI�Ȗʂ�����܂��B�Ⴆ�A�X�|�[�c�ŕ������Ƃ��ɉ������⎩���ɑ���{����o�l�ɂ��ė��K�ɗ�ނ悤�ɁA�{��͐l�������`�x�[�V�����Ƃ��Ă��L�����p�ł���̂ł��B
���̂��߁A�A���K�[�}�l�W�����g�ł́u�{��Ȃ��v��Ԃ�ڎw���܂���B�{��ׂ���ʂł͏��ɓ{��A�{��K�v�̂Ȃ���ʂł͓{��Ȃ��čςނ悤�Ƀg���[�j���O�����܂��B�{�����ʂ��A��������̓I�Ɋ����I���ł���悤�ɁA���̃X�L���Ƃ��ăA���K�[�}�l�W�����g��g�ɕt����̂ł��B
�A���K�[�}�l�W�����g�����ڂ����悤�ɂȂ����w�i�ɁA���l�ς̑��l��������悤�ł��B
���܂��܂ȉ��l�ς�C�t�X�^�C����F�ߍ����Љ�ւƕς���Ă������Ƃ������ŁA���̂Ȃ��ɂ͂܂��܂��A�������M���Ă������l�ψȊO�̂��̂�������Ȃ��l���������܂��B���̂悤�Ȑl�������A�����ƈقȂ鉿�l�ς����l�Ɛڂ���@����������߁A�{��𗭂߂��݂₷���Ȃ��Ă��܂����̂ł��B
�A���K�[�}�l�W�����g��g�ɕt���āA�{����Ǘ��ł���悤�ɂȂ�ƁA�{�邩�{��Ȃ��������̐ӔC�Ŋ����I�ׂ�悤�ɂȂ�܂��B���̌��ʁA�{��ɂ���ďo��Փ��I�Ȍ�����s����}���ł��A�K�Ȗ�������R�~���j�P�[�V�����ɂȂ�����悤�ɂȂ�܂����A�X�g���X���������܂��B
�ȑO�A���T��œ{����R���g���[��������@�Ƃ��āA���������Ē��������Ƃ�����܂����B
�{���Ă���Ƃ�����Ԃ�\���\���Ƃ��āA�u���ɂ���v�A�u�����ނ��ނ�����v�A�u�������v�Ƃ��������t������܂����A�����A�䎩���ɓ{�肪�萶���Ă���ȁA�ƋC���������A�u�̂̂ǂ��Ɂu�{��v�����Ă��邩�A�悭�ώ@���Ă݂Ă��������v�Ƃ��b�����܂����B
���ۂɁA���݂����������������āA�u�ώ@���Ă��邤���ɉ����Ȃ��ď��Ă��܂����v�Ƃ���������������Ⴂ�܂����B���Ȃ݂ɁA���́u���ɂ���v����ԑ����ł��B(-_-;)�@
�A���K�[�}�l�W�����g�ɂ́A�u�{���Â߂�u6�b���[���v�v�Ƃ������̂����邱�Ƃ��ŋߒm��܂����B
�u�{��̑Ώ��p�ɋ��ʂ���̂́A�u�{��ɔ��˂��Ȃ����Ɓv�ł��B���̂��߁A�����̓{�����������A�܂�6�b�҂��ē{���Â߂܂��傤�B�v�Ƃ���܂����B���̂���Ă��܂��ɍ��v���Ă����悤�ŁA�������Ȃ�A�Ȃ������v���o���Ă���܂����B
�@�܂��A�����g�̏ꍇ�A�q���̂��납��A�ʒm�\�Ȃǂɒ����Ƃ��āu���`���������v�ȂǂƏ�����Ă��܂����B
�����āA�䖾�@�̒ʂ�A���`���������A�u�`����ׂ��A�Ǝv���v�Ƃ������Ƃ́A�u�{��v���N���₷���Ƃ������Ƃł�����܂��B�ł����犩�P�������m�̃e���r�h���}�ȂǑ�D���ŁA���N���N���Ȃ���ςĂ���܂������A�������ɗ�V�O���߂��܂��ƁA���̒�����ȂɊG�ɂ������悤�ɁA���z�ʂ�ɂ͂����Ȃ��A�ƒx����Ȃ���v���m��܂����̂ŁA�u�{��v�̌��ɂȂ肻���Ȏ������@�m������A�\�Ȍ��肻�����瓦���o���A�ڂ��Ȃ��A������A�Ƃ������Ƃ�S�����Ă��܂��B
�u�{��v�ɑ��ẮA���̂悤�ȑΏ��������Ă��ǂ��̂ł́c�Ɛl���̏I���ɋ߂Â������A�v���n�߂Ă��܂��B
2023�N�@�u1���̕W��v
���i�������j�̂��Ƃ�
�\�\�\ �����܌o����54�200�u�������o�v
���鎞�A���ɂ͂��̂悤�ɖ@�������܂����B
�u�Ⴆ�A�F����B�����Ɉ�l�̗��l�����āA��������Ă���Ƃ��܂��傤�B�ނ͑傫�Ȑ�̂قƂ�ɒH�蒅���܂����B��������ނ͐쉈����������ƍl���܂������A��̂����瑤�͑�ϊ댯�ȓ��ł��B����A��̌��������́A���邩��ɕ����₷�����ł��B�����Ŕނ͌������݂ɓn�낤�Ǝv�����̂ł����A��̗���͎v�����ȏ�ɋ}�ŁA����������Ă��A���͂��납�A�n���D������܂���B
���炭�l�����ނ́A��݂ɐ����Ă��鑐���g���A��������ēn�邱�Ƃɂ��܂����B�����Ė����������݂ɒH�蒅�����̂ł��B�����āA�����ɐ��n�����ނ͎v���܂����B
�w���̔��͂Ȃ��Ȃ����ɗ��ȁB�����Ɏc���Ă����̂͐ɂ������炢���B�悵�I��������������A���̔��͌��ɒS���ŁA�ǂ��܂ł���Ɏ����Ă������Ƃɂ��悤�I�x
���ĊF����B������Ăǂ��v���܂����H�ʂ����āA�ނ͂������邱�Ƃŗǂ������̂ł��傤���H�v
��q�����͈�Ăɓ����܂����B�u����Ȃ��Ƃ���܂���I�v
���ɂ͂�����������܂����B�u�ł́A�ǂ�����Ηǂ������̂ł��傤���H
�u�t���I���͒u���Ă����ׂ��ł��I�v�ƁA��q�����͓����܂����B
���̐��������ɂ͔��݂܂����B
�u���̂悤�ɁA���͔��ɚg������@������܂��B����́A�n�邽�߂ł����āA�߂���邽�߂ł͂���܂���B
���̂悤�Ȗ@�𗝉������Ȃ�A���Ȃ������́A���Ƃ����̐������@�ł��낤�Ƃ��A�̂Ă�ׂ����ɂ́A�̂ċ���ׂ��ł��B�܂��Ă�A��@�Ȃ�Ώ��X�̎��B�v
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
���̂��Ƃ��b�ŁA�����̂Ă�ׂ��ł���Ƃ������Ƃ́A�[���ł����Ƃ��Ă��A�Ō�Ɏ��̐������@�ł��낤�Ǝ̂Ă�ׂ��c�ƌ����āA�[���ł�����͑����͂Ȃ��悤�Ɏv���܂��B
�T�̊�{�I�ȋ����̒��Ɂu�s�������i�ӂ�イ���j�v�Ƃ������t������܂��B����́u���t�╶���ɕ߂���Ă͂����Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł��B
�u�s�������v�́A�T�@�̊J�c�Ƃ��Ēm����B���l�i�{�[�f�B�_���}�j�̌��t�Ƃ��ē`����Ă���A�u�����i�ŏ����ꂽ���́j�͉��߂�����ł͂ǂ̂悤�ɂ��ς���Ă��܂��̂ŁA���̂��߂ɂ͂����ĕ����𗧂ĂȂ��v�Ƃ������߂ł��B
���ɂ̋������A�B����t���ʂ̕\�����g���Đ����Ȃ��������̂ƌ����܂��B���Ȃ킿�A�����ł͌��t�╶�������ɓ�����Ƃ����̂ł��B
���t�ł́A�����̍l����100%�\�����邱�Ƃ͂ł��܂��A��̎����ŁA�傫�����̈Ӑ}���ς���Ă��܂����Ƃ�����܂��̂ŁA���t�╶�����g��������鑤���[���Ȓ��ӂ��K�v�ł���A���t�̎g�����͐T�d�ɍs���ׂ��Ɛ����Ă��܂��B
������Ƃ����đT�ł́A���t�╶�����g��Ȃ����Ƃ����ƁA�����ł͂���܂���B
�u�s�������v�Ƃ����u�����v�ŏ����\���Ƃ���ɁA���ꂪ�ł��@���ɕ\��Ă���ǂ��Ⴞ�Ǝv���܂��B
��肭�\������̂͂Ȃ��Ȃ�����ł����A�u�\�莆�֎~�v�Ƃ��������A�ǂɓ\��悤�Ȏ��Ȗ������܂�ł���Ƃ������������ł���Ǝv���܂��B
�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E�E
�����P�V�N�i�Q�O�O�T�N�j�{�������z���Ă��������A�Z�E�ɏA�C���Ă���P�V�N���o���܂����B���N���炨���̃E�F�u�T�C�g���J�݂��A�������̕W����X�V���ĎQ��܂������A�{���ɕ����ɂ��Ă��`�����邱�Ƃ̓����Ɋ����Ă���܂��B���̂悤�Ȓ��ł��A�����邱�Ƃ��ł����̂́A�ЂƂ��ɁA�ǂ�Œ����Ă������������������������ƁA�S���犴�Ӑ\���グ�܂��B�����K���A��ǂݒ��������z�����������������������A��ϗ�݂ɂȂ邾���łȂ��A���w�E�����邱�Ƃ��A�����g�̋C�Â���w�тɂȂ���܂��̂ŁA�{���ɗL��A����������낵�����肢�\���グ�܂��B
�܂��A����ŁA���t�Ƃ͑S���ʂ̚g�ł����A�ŋ߁A�����V�������A�����d�₨��ɂ��āA�V���ɂ����k����@������������܂����B������̕��Ƃ��b�����Ă��ċC���������Ƃł����A���������ł��@�h��A���܂ł̂����ɂ������̋�����������������̂ł��B�����艺�̔N��ł��ƁA����╧�d�A�������ɂ͂��܂肱����肪�Ȃ��A���d��ʔv���w�����Ȃ��A��������������A���߂��炨���̋��{���ɔ[���������Ƃ������������Ă��܂����B�E�`�����������b�ɂȂ��Ă���މ�����́A�u�ŋ߂͐V������̌����͂قƂ�ǂȂ��A��I������ł��B�v�ƒQ���Ă��܂����B
���̐މ�����Ɍ��ĂĂ�����������ɂ���܂����J�̋��{���ɂ��낻��P�O�O�̋߂������蒸�������Ƃł��A�������蒸����Ǝv���܂��B
���܂ł̂����ɔ����Ă��鍂��҂̕��Ƃ��b�����Ă��܂��ƁA�@�h�╧�d���A�O�q�̗Ⴆ�́u���v�ɂȂ��Ă��܂��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂����B
���߉ޗl���A�F���u�E�`�͖{�莛������B�v�u����T�@������B�v�ƌ����Ă���̂��������ɂȂ�����
�u����͈�̂Ȃ�̂��Ƃł����H�v�Ƌ�����邱�Ƃł��傤�B
����������̕ϑJ�ɔ����A���R�A�����{�̎d�����ς���Ă����킯�ł�����A�����Ƃ��Ă͂�����P�[�X�ɑΉ�����K�v�ɔ����Ă��Ă���܂��B�ł��̂ŁA������̕����A���q�̑�ɁA�]���̉��l�ς������t����̂ł͂Ȃ��A�_��ȑԓx�ŗՂ�Œ��������ƐɊ���Ă���܂��B